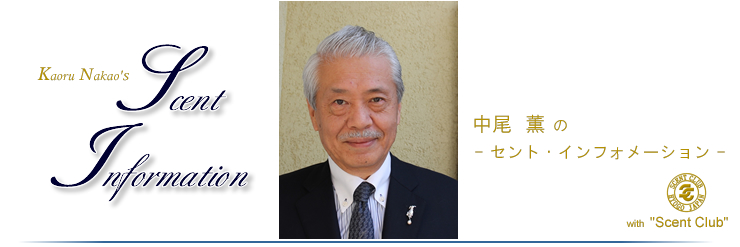 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ルーティン 平成28年4月1日 ラグビーの五郎丸ですっかり有名となったルーティン。 "routine work"という言葉が慣用語として使われており、決まった手順で繰り返し行われる定常作業、あるいは日常の仕事、というような解説が辞書ではされている。 創意工夫の必要ない業務、つまらない仕事、との解説も見られるが、私達はむしろ最も重要な要素として使ってきた言葉のように思う。 この定着した正確な仕事をこなせなければ、歯科医療は成り立たない。 学問体系に基づいた治療を実践するには最も大切な基本的な技量遂行の事を指している。 新人歯科医師にとっては大変難しく、ある程度の水準に達するまで相当の年月を要する。 そして、初めて創意工夫の出来る歯科医師が誕生することとなる。 だからルーティンは歯科医師の基本なのだ。 改めて五郎丸選手が示してくれたキック前のポーズは、恥ずかしいという気持ちを超えたゴールを決めるにあたっての自身のおまじないのようなもので、とかく先立つ見栄えとかを払拭させてくれた。 あれをかっこ良いと感じたのは日本チームの活躍によってであり、弱いチームだと、これほどセンセーショナルとはならなかったに違いない。 日常生活のルーティンは、人それぞれ異なる。 起床時間も睡眠時間も食事の内容も量も、全て違う。 家族でも違うのだ。 神仏への礼拝も色々。 何気ない所作で、神棚にパンパン! 私は可能な時は仏壇に就寝前手を合わせ、おリンをチンチン。 別にどうってことはないのだが、これで気が休まるだけのこと。 ご先祖様が「よしよし・・!」と思ってくれているような錯覚かもしれないが、その日の終わりの儀式だから誰に干渉されることもない勝手なルーティンである。 教育とか高尚なものではなく、平時のルーティンは皆さんで固有の大切なものだろう。 それを崩すと一日中どうもしっくり行かないような気がする。 あまり神経質になり過ぎるのもどうかとは思うが、一定のリズム感が定着している方が生きていきやすいように感じる。 歯科医師という職種で最も慎むべきことはちゃらんぽらんなことだが、裏返すと自分のルーティンを正しく持ち合わせた誠実さが問われているのだろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
歯科医療今昔 平成28年3月1日 明治維新後、近代医療の導入が図られた。 江戸時代の医療は漢方医、そして幕末時には蘭方医がいた。 御殿医という大名に仕えたお医者もいれば、町医者もいた。 今のような資格・規定もなく、誰でもなれたという記述が多い。 士農工商という身分制度の中では、特別職的な状態であったらしい。 神官や僧侶とかに位置づけられていたのだろう。 目まぐるしく変化する世相だが、歯科医療もすさまじい勢いで変化を続けている。 つまり、専門教育を受けた正規の歯科医師が世に出てまだ100年ほど、その間に太平洋戦争を挟み、世の中がすっかり変わってしまった。 変化の速度が、明治以前の100年とは比較が出来ない。 現代を生きる者として、戦後世代としての歯科医師像を勝手ながら考えてみよう。 一応75歳まで現役の歯科医師と仮定すると、昭和15年生まれの歯科医師~平成4年生まれの歯科医師が歯科医院を開業している。 25歳~75歳ということは50年の幅がある。歯科医学の進歩も目覚ましいものがあるが、それよりも世の中の変化の方が激変している。 戦後奇跡の経済成長を遂げた日本は豊かになり、人口増と共に全ての歯車が好循環した。 公害問題を克服し、安定した社会になったが、今また少子高齢化問題で新たな局面を迎えている。 2015年団塊の世代が後期高齢者となる頃に、高齢者はピークアウトし、その後少子化と労働力現象の時代を迎える。 当然、医療内容も変化し続ける。 地域包括医療により子供からお年寄りまで地域内皆で手を繋ぎ合い生きる街を目指し行政は躍起となっている。 医療費抑制の隠れた秘策とも言われているが、それらが達成された後は、どのようなビジョンがあるのか現在は分からない。 私達歯科医師は真面目にコツコツと虫歯治療に対峙し、今では子供達の多くは虫歯の痛みを知らない。 歯周病も、今後徐々に減少してくれるよう啓発活動が続けられている。 歯科治療を行う歯医者さんというイメージよりも、歯と口を管理してくれる歯医者さんに変化して行くように思うが、たった数十年でさえ先の事は分からない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
病は気から? 平成28年2月1日 昔から、病は気からと言われることがある。 臨床病理において、風邪症候群に罹患した状態は気の問題ではなく、齲蝕(虫歯)も気とは無関係。 我々医療人の日々の臨床の多くは実態に基づいた疾病治療である。 しかし日常生活において、この気というものが非常に大きな問題の場合がある。 心技体とはスポーツで特に好まれて使われている。 心の集中度合であり、渾身一滴による最大力を発揮させることも可能。 裏を返せば、気合が入らなければ何事においても成せないとも言える。 気持ち悪いとか、気分が乗らないとか、気になるとか、気がそがれるとか、日本語ではたくさんの気を表す言葉がある。 気というものを非常に大切にしてきたのだろうと思われる。 心の葛藤により、選択が180°代わる事もある。 気が乗らない日は、何をしても上手く行かないという経験は誰にでもある。 気持ちの持ちようにより、随分と違う結果も経験する。 気力が湧くともいうが、気が張っていないと前向きな行動が出来ないことも多い。 最近、心躍らせる日本ラグビーの活躍ニュースにワクワクさせられる方も多いだろう。 特に、五郎丸のキック前のポーズが大人気。 あの集中ポーズもパフォーマンスではなく、自身の気持ちを一定のリズムの中で、キックを成功させる空間世界に入るためのものだろう。 祈るようにも見えるが、ご本人は外観よりも自己集中するための強い信念から編み出されたもののようだ。 ことほど左様に、気持ちは生きて行くために極めて重要なものだ。 気持ちとは形に表せないものだから、ともすると誤解を招くようなこともある。 何故、ネガティブな行動ばかりするのか? どうしてもっと溌剌としないのかと言われても、中々難しい側面もある。 何かの背景があり、気分がすぐれない場合、それを察して家族が、あるいは周囲の者達が配慮することも大切だが、そういう発信も出来ずにいて周りも気づかないこともあるだろう。 家族・社会が過度に気遣うのではなく、それとなくアンテナを張り巡らせて受信に心がけていく、そういう世の中であって欲しいものだ。 それにしても、年齢と共に気力も衰える。 偉そうなことは言えない自分の現実を見つめ直さねば・・・!? |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
キーボードを使わない時代 平成28年1月3日 パソコンには不慣れでも、無ければ日々が暮らせない自分になっている。 10数年前、パソコンの手ほどきを懇切丁寧にしてくれた友は、当時すでに 「キーボードを使わない時代が来ますから・・・」 と言っていたのを思い出す。 まさか、そんなことはあり得ないと思っていたが、現実にスマホ時代となりキーボードレスの時代が来ている。 スマホだけの方も多いと聞くが、タブレットを持てば画面の大きさ等もパソコンに遜色ない。 文字操作も慣れれば良いのだろうが、ワードやエクセルなどの繊細かつスピーディーなことは僕には無理だ。 現在、デスクトップ1台・ノート1台・タブレット1台・スマホ1台を使っている。 デスクとノートは同期しているが、メンテが結構面倒。 タブレットは歯科医師会で使っているが、OSが異なるので誠に使い勝手が悪い。 ダウンロードされた役員会資料閲覧にだけ使っている。 携帯スマホは便利だし、四六時中手元にあって活用する。 残念ながら電池があまり持たないので出先では困る事がある。 タブレット・スマホともにメモリ媒体記録なので立ち上がりが早く、面倒な操作も格段に楽になった。 HDD仕様のパソコンではこの点で見劣りするが、今のところ手放せない。 いっそ、今のHDDをSSD換装したいと思う。 いやはや、アップテンポな世の中になったものだ。 決してITおたくではないが、HP・ブログ更新はじめ、情報収集発信には欠かせないのだからやむを得ない。 昔なら庭いじりでもしながら余生を楽しむ年なのだが、様々なものに振り回され一日の時間的余裕がない。 名工とか物づくり日本とか書画骨董とかとは無縁の世界が、ITの世界のように感じる。 珠玉の一品というような感覚は、パソコンには無い。 でも進化し続けるITに付いていかねばならない、義務のような気持がある。 様々な批判もあるようだが、音声入力で道案内される味を覚えてしまうと元には引き返せない。 そのうちに、冥途へも音声入力で三途の川へ連れて行ってくれる時代になるのかもしれない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
星降る夜の散歩 平成27年12月1日 小さい頃、父親に手を繋がれて夜道を歩いていた。 晴れた夜には星がキラキラと綺麗だなということを覚えている。 すると、にわかに親父が僕に向かい 「薫 綺麗な星空だね 星と比べるとヒトはほんの一瞬生きて・・・ どうってことないよ・・・」 というようなことを呟いた。 正確な言い回しは覚えていないが、要するにこういうような事を言ったことだけ記憶の奥底に残っている。 たぶん、小学生低学年の頃だっただろう。 だからからか、何の疑問も無く、その呟きだけが残っている。 質問もしない、会話でもない、ただ親父の独り言のようなものを、何故だか幼心の僕に刻んだ独り言が、今の人生を形どっているように思えて仕方がない。 親父の独り言の深層心理は分からない。 戦争体験者として死線を超え抑留先から帰国、その後僕が生まれた。 その死生観は現代とはかけ離れたものがあっただろうし、僕という授かった命に生きる実感もあったのだろう。 星が瞬く瞬間よりはるかに短いヒトの人生なのだから、精一杯生きろ!というメッセージだったように思う。 年寄っ子だった僕のことを心配しながら、僕の学生時代に逝った。だから親子喧嘩やら何も無かったし、しっかりと話をした思い出もない。 代わりに母親が長命だったので、その分随分と親孝行させてもらいつつ、長い話やら愚痴やらを聞かされていた。 人間勝手なもので、都合の悪いことは忘れ去り良い事だけが蘇る。 僕には二人の子供がいるが、手を繋いで夜道を散歩したことは無い。 とにかく夜はいなかったし、たまの休みに遊園地に連れて行っただけ。 気の利いた話などしていない。 随分と良くない父親だったのだろう。 その子達も巣立ち、家内と二人 (と言っても、大きな犬が二頭いるが・・・)。子育てに正解など無いが、お手手繋いで星降る夜の散歩の呟きとは、僕の親父は名監督だったのかもしれない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
医療費と社会保障費 平成27年11月2日 医療への政府補助金が莫大となり、医療費はパンクするという医療亡国論がことさら声高に言われた事もある。 政府補助・助成金は国民の税金であり、すなわち国民相互の互助である。 医療サービスは、実態として医療サービス産業であり、GDP・消費を押し上げることに貢献しているのだが、残念ながらそれらに加えられることはなくお荷物扱いをされている。 公助・自助・共助・互助(最近、互助が加えられたが、そもそも医療保険全体が互助的なもの)とも言われる医療だが、医療費は自己負担金・国保と社会保険基金からの保険給付そして政府からの補助金で賄われる。 結果的に全て国民の財布からの出費であり、共助システムで循環している。 消費低迷によるデフレ脱却が日本経済の喫緊課題だと言われるが、医療も消費財と同じく医療サービスとしての位置づけがなされれば消費押し上げ要因の大きな柱となる。 約40兆円が総医療費として平成25年度数値として厚労省HPに掲載されている。この数字の肥大化を皆こぞって心配している。 介護保険も含めて医療福祉への国の対応は、社会保障としてひとくくりで論議されることが多い。 年金・生活保護・児童手当・介護そして医療等が、社会福祉。 医療は利益追求してはならないと規則で謳われている。様々な規則の中で運用される国家主導統制経済の最たるものだ。 医療機関の医療収入・医療経営と社会保障という言葉使いはどう考えても現状に馴染まない。利益追求をしてはならないという規則は分かる。 しかし、利益が出なければ医療機関は死に体であり立ち行かなくなる。 つまりは、綺麗な言葉を並べての国家統制ということとなる。 社会保障の枠に入れられた制度としての医療であるので、国民皆保険が持続し、高い質と安価な医療提供が全国津津浦浦で可能となっている事実は尊重されなければならない。 社会保障制度の内での医療の位置づけを崩せば限りなく自由競争型医療となる危険性もある。 全ての整合性を持たせた制度変革がなされれば良いのだが、中々難しい問題のようだ。例えば、現状の制度の枠内で、医療サービスを生産性のある産業としての立ち位置と解釈して変化を持たせるだけで、相当程度の意味合いと内容が好転するのではないだろうか。 つまり雇用創出・器材薬剤・機器整備・建築など多岐に渡る生産性に寄与している医療と言う産業の定義づけを変えるだけで、随分と豊かな国民生活への寄与に貢献していることとなる。 社会保障制度として医療を捉えると、将来的負担増への歯止めを論議されても致し方ないのだが、生産性ある社会保障として位置づけてもらえれば、一定の範囲で国民の皆様の理解が得られるようになるのではないだろうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
鋭い筆致 平成27年10月1日 文章を書くことは大変だし、苦痛な時でもある。 伝える相手、目的、説得性、等により文章の内容は大きく異なる。 説得して同意を得るというのは最も困難だろう。 情緒的詩的感覚を訴える内容はさらに難しく、不特定の方々を感銘させる珠玉の名文は恐らく作者の意図的なものではなく、自然な心が文章に反映されたものだ。 HPを更新し続けて久しいが、視点論点がぶれて回顧的な内容に偏って来た。 これでは、ただ思い出を綴っているだけで実につまらない。 歯科医師として歯科医師会会員として、何かを問いかけ、新しい方向性を提示する問題提起をしなければ、本来の私のHPの役割を果たしているとはいえない。 と、ここで筆が止まった・・・。 ・・・!? 山積する問題を、どのように解決するべきか? なる様にしかならない、放っておけば勝手に何とかなる、そういう考え方もあるだろう。 それでは前向き迅速な対応とはならない。 合理的でコンパクト、機敏な行動が可能となる世の中に変化させなければならない。 思いつくままに問題を考えてみる。 社会保障の中の医療費は莫大な金額となり、支払者である保険者が悲鳴を上げていることが最大であろう。 会社の保険組合は社員から月々保険料を徴収して、社員とその家族が受診したら支払基金を通して医療費は支払う。常に徴収額と支払額の帳尻が合っているなら問題とはならない。 近年では支払額の方が上回り赤字基調の保険組合が増加している。 政府補助金などを投入し、何とかやり繰りしている。 だから、医療費削減と言う大合唱が起こっているのだ。 それはそうだろう、組合も社員のために健康を維持管理するのに赤字を垂れ流していれば、やがて本業の会社にも響くし、政府も様々な助成金の金額が膨大となり、何とか医療費を引き下げたいと躍起なのだ。ここまで書いてくると、医療費削減には妥当性があるように聞こえるかもしれない。 ところが、日本中の健康保険組合は一本化されていないし、国民健康保険もたくさん存在する。 これらの統合は昔から言われているがいまだ実現していない。 総医療費を削減して国民は困らないのか? 医療機関は困らないのか? 困るのだ! 社会保障という枠からはみ出した医療は最早日本の医療制度とは言えないから、今のままで国民皆保険を維持して行くには、医療費削減しかないという荒っぽい論法だ。 次回は、これらの点について考えてみたい。 鈍い筆致となってしまった! |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ネット環境と加齢 平成27年9月1日 ネットサーフィンという言葉が使われ始めて久しい。 ウェブ上で次から次へと興味があるサイトを閲覧し様々な事柄を検索することだが、スマホにタブレットとより迅速に手軽に使える時代となった。 さらに、もはやPCは不要で、スマホがあれば良いという世相となって来ている感さえある。 ネットによる犯罪も多発し、国家的規模の大きな問題となっている。ワンクリックで全世界と繋がる訳で、大きなリスクも抱えている。 私自身すでに高齢者となっているので、遠くない将来、正常なネット利用が出来なくなるのではないかと少々心配となっている。 自分の責任でPC環境を保全し、常日頃から不正な受信をしないように心がけねばならない。 まさに自己責任なので、便利さ以上に細心の注意が必要。 故意にではなくとも、うっかりしたミスが起こらないとも限らない。 運転免許証では高齢者の免許証更新に際して一定のハードルが設けられているし、自主的にあるいは家族の勧めによって運転をしなくなる方が多い。 PCに関しては、時代背景的にPCが全く存在しない時代を過ごした高齢者もおられ、高齢者全員がPCを扱っている訳ではない。 ただ、これからは全ての国民がごく普通にPCに触れる時代が来るので、高齢者のPC環境をどのようにするのかは社会的問題となる可能性がある。 ネットバンキング初め、お買い物まで手軽にネットに依存する時代だが、頭の回転が不自由となった際に、何のためらいも無く不正を見抜けずクリックした場合には、後日とんでもない不利益を被る事も予想される。 朝から晩まで寝る時間も惜しんで見続けている人が高齢者になった時にどうなるのかも気がかりだ。 自由空間のネットではあるが、家族あるいは周りの者の助言や手助けが高齢者には不可欠な時代が到来するのはそう遠くない現実ではないだろうか。 便利な環境の保持には個人の管理責任という義務も生じる。厄介な時代となったが上手に付き合いながら、家族をはじめとした周囲の方々との常日頃の連携・助言そして相談・声掛けが必須だろうと思う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
時の流れ 平成27年8月1日 生まれてこのかたの記憶というものを、辿ってみた。 5歳ぐらいの事は、話題によって思い出す場面もある。 小学校の6年間は、連続性では思い出せない。 中学生の頃も、同じだ。 高校生時代のことは、かなり鮮明に思い出すこともある。 その後の人生となると、節目である結婚とか子が生まれた時とかで思い出される。 自分の中での大きな変化の時を区切って考えているようだ。 アルバムを見た際には、当時の事がパッと記憶を蘇らせる。 ある時代からアルバムも無く写真だけが乱雑に保存されていて、掃除の折などでしか目に触れない。 10年ほど前からデジタル写真が普及し、パソコンで見ることが出来る。 これは便利だし、時系列でパソコンが見せてくれる。 記憶というものを辿って自分の人生を意味づけようと試みても、現実には大きな出来事だけがフラッシュバックのように蘇るだけで平素の生活の記憶はおぼろげでしかない。 つまり、意味づけようにもそれほど意味ある生活を送っていた訳ではないように思える。 そういうものなのだろう。 過去を振り返り歴史認識云々という政治的なニュースや活字が躍る時代だが、人々は詳細な過去を克明に覚えている訳ではなさそうだ。 結構、自己都合で忘れようとしていることもあるようだし、さりとて良かった筈のことも忘れ去っている。 世界史・日本史と学生時代の試験では苦しめられたが、社会人となり歴史小説などに触れると興味深いことが多い。 しかし歴史が好きというほどでもなく、また歴史を一括りで語るほどの知識も無い。 過去を教訓に現実を見据えて明日に向かうということが一般的に強調されるのだが、それほどシャカリキになるまでもなく、とにかく今を生きるということで精一杯なのが人生なのだろうと思っている。 時の流れは無情であり、酷でもあるが、時を刻むという有限の空間の中に身を委ねるからこその楽しみがある。 例え認知症で1分前のことを忘れる状態となっても、今を生きる瞬間を楽しむ心構えこそ人の尊厳ではないかと思う今日この頃。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
目に見えない境目 平成27年7月1日 国境・県境・行政区分け等、明らかな境目というのがある。 頭の中では常に、この境目を意識して生きている。 道路一本挟んで、市県民税も異なる。 土地の境界線でも争いが起きることがある。 領土問題となると戦争も起きうる。 境目とは、実に厄介なものだ。 また、目に見えない境目があるので世相何かとややこしい。 人生の境目というものは誰しも経験するが、その境目は後になって気づくものだ。 あの時こうしておけばという事は、枚挙にいとまがない。 明確な境目が見えていれば、あんなへまは打たなかったのにと反省する。 しかしそれが人生だし、何もかも上手くいく筈もない。 例えば、1点に泣くこともあるだろう。 1点の違いで大学も不合格になるし、スポーツでも負けは負けとなってしまう。 泣くに泣けない結果が、後々の人生を大きく変えることもある。 仕方ないことではあるが、不条理とかという刹那的言葉で自分を納得させてしまう。 運命の境目というか、自力ではどうにもならない分岐点というものもある。 19歳の夏、神戸は大水害に見舞われた。 国鉄電車が甲子園口駅で立ち往生という兄からの電話で、僕は車で迎えに行った。 土砂降りの雨の中、次第に車の周囲は水浸しとなり、少しハンドルを右に切った時、車がフワッと浮かぶような感じとなり、右前方から何と道路より下に下がっていった。 しまった、と思う間もなく車は本当にプカリと宙に浮き、やがて前方から沈んで行った。 そして、少し流された感じで斜めになって止まった。 その時、車内は腰上まで水に浸かっていた。 まだ何が起こったのか理解不能、それよりも怖い親父の顔が浮かんでいた。 そうこうしていると警官が二人、車外で騒いでおり、早く出ろ!と叫んでいる。 手動の窓を開けて窓から警官に引っ張り出された。 通りがかったパトカーの警察管だった。 甲子園の疎水に車が落ちたのだ。 浮いた車は、テールを水道管かガス管に引っ掛かけて止まっていた。 引っ掛かっていた下流は暗渠となっており、そのまま海に繋がっている。 おしゃかになった車を憂うより、助かった命に唖然とした。 幾重にも重なった幸運という運命の分かれ目ということがあるものだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
我が家 平成27年6月1日 我が家は、神戸東端の国道2号線沿いに位置するちっぽけな診療所兼住まいだ。 最近では住まいを別にする診療所が多くなり、昔ながらの住まい兼診療所は珍しくなった。 ここで育ち、幼稚園・小学校・中学校・高校(要するに学区内の小中高)・大学と全て自宅から通学した。 大学卒業後は神戸市内の大学付属病院に勤務したので、やはり自宅通勤だった。 結婚して5年間は、自宅近くのマンションに住んでいた。 その後開業したのだが、やはりこの地で家を建て直しての開業。 だから、いままで本山から離れたことがない。 唯一、3ヶ月間大学からの派遣で三菱金属明延鉱山診療所に赴任した。 つまり、ほとんど今の自宅で人生を過ごしている。 大学・就職で親元を離れる場合が多いようだが、私のようにずっとこの本山という地で過ごすということは稀なことなのかもしれない。 成行きでこうなった訳で、選択したこともなければ、しがみついたのでもない。 事実、二人の子供は本山を離れ所帯を持っている。 我が故郷、神戸本山に住み着いて何を考えるかというと、別段何も考えていない。 裏返せば、この本山しか知らないのだ。 かといって街の隅々まで知っているかというと、そうでもない。 点と点しか分からない。 生活様式というものは実に単純で、駅に行く、決まった所に買い物に出かける、歯科医師会の用事で出かける、同窓会等の懇親会で三ノ宮に出かける、友達と飲み食いに出かける、たまに旅行に出かける、それぐらいだ。 ゴルフや野外活動的趣味も無く、読書や原稿書き程度で日々を過ごしている。 爺くさいと言われても若い頃から、この生活リズムは変わっていない。 故郷は良いものだ。 時に旅行などで家を留守にして帰宅すると、ホッとする。 あばら家でも、行き先の旅館ホテルがどれほど素晴らしく立派な所であっても、我が家に帰ると落ち着く。 故郷に帰る本能が人には備わっているのだろう。 阪神淡路大震災で壊滅的被害に会った我が町も、今では平穏な生活臭が漂っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
春爛漫(はるらんまん) 平成27年5月1日 一面に花々が咲き乱れ光輝き溢れる春を指す言葉だが、響きが実に良い。 山花開似錦 澗水湛如藍(山花開いて錦に似たり 澗水(かんすい)たたえて藍の如し)という禅語がある。 山々に咲く花は錦のように咲き乱れ、谷は藍のような水を豊かに湛えている・・・、そして説法では云々・・・なのだが、難しい。 春うららという表現もある。 のどかで明るいという意味だろう。 春のうららの隅田川・・・という滝廉太郎の唱歌は「春」という題名。 懐かしい思いがふつふつと湧き上がるが、人によっては競馬馬の「ハルウララ」を思い出す方もおられるだろう。 辞書で春の季語を調べると、膨大な表現法がある。 日本語の持つ豊かで繊細な言葉にあらためて驚き、自分の無知に恥ずかしさを覚える。 50の手習いともいうが、今更勉強する気にもならず、ぐうたらに日々を過ごすことを決め込んでいる。 まだまだチャレンジし続け、奮励努力せよと自分のどこかで聞こえてくるのだが、叱ってくれる親もいないのだから勝手気ままにする方が上回っている。 どんなに年を重ねても春の到来は嬉しいし、漠然とした希望の目が開いてくれたような気にさせてくれる。 草花の美しい力が、人に生気を甦らせてくれるのだろうか。 桜さくらさくら、日本中が春で弾け心浮き立つ。 寒い冬あればこその春だが、日本人はことさら春到来への執着心が強い。 百花繚乱の春も、やがて梅雨から夏になる。 四季折々の美しさに感動を覚えるのだが、初夏に移り行く頃、5月病というのがある。 希望に胸膨らませ、環境にそろそろ慣れてきた連休明けに、うつ状態になる人がいる。 何かもの悲しさに苛まれ、激変した環境に付いていけない場合もある。 それはそれで克服しなければ、社会生活、学生生活を営まれなくなる。 春に騙されず、錯覚だと言い聞かせ平常心を養っていかねばならないのは、老若男女全ての人に言える。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ダイナミックに変化する世の中 平成27年3月24日 世の中は、徐々に緩やかに緩慢に気づかない程度に変化をして行くと感じる。 日々の生活の中で、周囲がどのように変わっていくのか体感する事は少ない。 冠婚葬祭という変化は、個人的変化として受け止められる。 景気の変動は、どうだろう。 政府が公表する指標を肌で感じる庶民は少ない。 景気が良いと言われていても、自分のところの景気には直接関係がなさそうで、いつしか不景気な世になってしまっている。 その不景気感に関しては、割と実感する。 何故か、庶民感覚では景況感はずれる。 大企業の指標に左右される景気動向なのだから無理もない。 果たして、庶民はいつの日も金回りが悪いと愚痴の一つも出てくるというものだ。 生まれてこの方の世の変動をテレビ報道などで見る機会があると、随分とダイナミックに変化している日本に驚く。 気づかないだけで、実は大きな変化は起きているのだ。 今が普通で明日も同じだろうという感覚に人は陥るが、現実には様々なことが世の中では起きており、いつしか大きく変わっている。 良くなる変化かどうかは分からないが、確実に変化して行くのだ。 世の時間軸と個人の時間軸では、流れ方が異なるのだろう。 目ざとい人は、素早く自分も変化し何かを成すこともある。 私など、世の中に付いていくだけで精いっぱいだ。 今日は、季節が逆戻りしたように寒い日だ。 でも来週には一斉に桜が咲き、春が来るらしい。 その変化を楽しみにしていたい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
親孝行子孝行 平成27年3月2日 子供を躾ける親、子供に手がかからなくなった後も何かと子供のことばかり心配する親・・・子育てに王道は無いと言われる。 両親の血を引く子供は、確実に親に似ている。 姿形は親に似ていることは外見的に確認可能だが、性格や資質もやはり似る。 形では比較が出来ないので、似つかわしくないとイラつく親もいる。 しかし、ある程度親に似ている。 トンビが鷹を生むとか言われる親子もいるが、同じ鳥の仲間であり、猿が人間を生んだという事では無い。 どこか通じている所があるのだ。 育つ環境の中でどういう努力を重ね続けたかということが、学習と言う言葉で表される。 勉強に限らず、人が真似をし、マネブという行為が学ぶという事に繋がると言われている。 どれほど学ぶかにより、その人の個性的生き方となる。 親が子にどのように関われば良いのか、子育ては深淵で悩み深いもの。 ようやく大人になった子に、あれやこれやと節介を焼く親もいる。 どこまで行っても親は子を心配する。 どのあたりで子離れが出来た事となるのかは、人それぞれなので分からない。 しかし、いつの日か、子が親の事を心配する時がくる。 ここで初めて子育てということに終点が見えた事となる。 目出度しめでたしということかもしれないが、これで親の人生が終わる訳ではない。 豊かで健康快適な日々を送ることが長く続けば良い。 ただ、長い老後の中では不自由な状態となる場合もある。 老老介護という社会現象も生じている。 何とも切ない事だが、超高齢化ということはそれだけお金もかかる。 そのあたりが、個人でも国でも大きな問題となっているのかもしれない。 お金だけではなく、体力も気力も親の面倒には必要。 私は両親を見送って久しいが、まだまだ親の面倒を見ている友も多い。 複雑な社会構造となりつつある日本という国。 親子関係、教育の課題、高齢化に関わる諸課題は、一連の流れとして世界の中では未経験な状態。 世界のお手本となれるよう、英知を結集しなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
思い出の捨て方 平成27年2月2日 結婚し、子供が出来、家庭に仕事に邁進していた壮年期。 思い出作りにも熱心だった。 写真を撮り、子供達の記念となるものを大切に残し、折に触れ思い出として振り返ることがあった。 今この齢となり、それらを子供や孫達に見せても、「あ、そう!?」 と見向きもしない。 思い出とはそれぐらいのものなのだろう。 夫婦だけの思い出もことさら今更という感があり、心の中に思い出を残し、記念となるものには余り意味がなくなってきた。 心の思い出も、やがて頭から消えて行くことだろう。 祖先を敬い今があることに感謝をすることは、極めて重要なことだと思う。 墓参りをし、仏壇に手を合わす・・・先祖を供養し、法要を営む日本人は多い。 ただ、ひい爺さんより前の先祖のことを知るすべはなく、過去帳やら家に伝わるものを大切にしている方もおられる。 しかし、1万年前とかのタイムラインでは、先祖の伝聞さえ分かる筈もない。 結局は、思い出というものは生きている者たちに限られた懐かしみなのだろう。 忘れてしまいたい思い出もあるだろうし、綺麗さっぱり忘れることも大切な場合もある。 思い出の品も思い切って捨てるのが本当は良いのだと思う。 亡き両親の品々も、納戸に封印されたまま。 いっそ捨てておいてくれたらと思う事がある(薄情な息子ですね)。 和ダンスを下から上へと見た事があるが、着物がぎっしりと詰まっているだけ。 引っ張り出す元気もなく引き出しを閉めた。 お札がチラリとでも見えたら隅々まで整理したのにな~・・・。 とかく、人は勝手なものである。 家の中はガラクタだらけなので、あちらこちらに千円札50枚ぐらいをランダムに潜り込ませ、奥の奥に万札を1枚だけさりげなく忍ばせておく。 今、こういう作戦を計画している。 チラッとでも金目が見つかると、恐らく家中綺麗に整理してくれることだろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
医療費と社会保障費 平成27年1月5日 新年、明けましておめでとうございます。 本年もどうぞ、よろしくお願い申し上げます。 さて・・・医療は、GDPを押し上げる成長産業だ。 医療への政府補助金が莫大となり、医療費はパンクするという医療亡国論がことさら声高に言われた事もあるが、それは間違っている。 政府補助・助成金は国民の税金であり、すなわち国民同士の互助である。 医療サービスは、実態として医療サービス産業でありGDP・消費を押し上げることに貢献しているのだが、残念ながらそれらに加えられることはなくお荷物扱いをされている。 公助・自助・共助・互助(最近、互助が加えられたが、そもそも医療保険全体が互助的なもの)とも言われる医療だが、医療費は自己負担金・国保と社会保険基金からの保険給付そして政府からの補助金で賄われる。 結果的に全て国民の財布からの出費であり、共助システムで循環している。 消費低迷によるデフレ脱却が日本の喫緊課題だと言われるが、医療も消費財と同じく医療サービスとしての位置づけがなされれば消費押し上げ要因の大きな柱である。 30数兆円が医療機関に支払われ、この数字の肥大化を皆こぞって心配している。 サービス消費なのだから、多くの場合入ってくるお金を上回る使い方はしない。 介護保険も含めて医療福祉への国の対応は、社会保障としてひとくくりで論議されることが多い。 年金・生活保護・児童手当・介護そして医療等が、社会福祉。 医療は利益追求してはならないと規則で謳われている。 様々な規則の中で運用される国家主導の最たるものだ。 保障というと、あたかも国が面倒をみてくれる制度のように考えてしまうが、そうではなく国民全員の互助制度であり、国家財政で全てを賄ってくれている訳ではない。 国にとって誠に都合のよい言葉である社会保障の中での医療の位置づけには、実に不適切な言葉遣いと言わざるを得ない。 医療機関の医療収入・医療経営と社会保障という言葉使いはどう考えても現状に馴染まない。 利益追求をしてはならないという規則は分かる。 しかし、利益が出なければ医療機関は死に体であり立ち行かなくなる。 つまりは、綺麗な言葉を並べての国家統制ということとなる。 これから先の在るべき未来の医療費というものを考えなければ、若い有為な医療人は育たないのではないか。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
人を見る目 平成26年12月1日 人生は社会との繋がりであり、人間関係というご縁の連続で成り立つ。 先生、友人との、偶然ともいえる出会いが生涯を決定することも多い。 「朱に交われば赤くなる」ということで、思わぬ人生展開もあるかもしれない。 自分自身がしっかりしておれば何の問題もないと思われがちだが、どうやらそうでもなさそうだ。 やはり、人との良好な関わりがあって初めて豊かな人生を歩んで行ける。 ここで人を見る目が大切となるが、それはそれで大変難しい。 全く同じ人が二人いるとする。 片方は、愛想よくにこやかで機転が利き実にフレンドリー、もう片方は不愛想でとっつきにくく気の利かない人。 どちらを良しとするか、普通の人なら前者を選ぶだろう。 ところが、往々にしてそれは間違いのこともある。 調子のよい人は要注意と昔の人は言った。 誠に誠実で本当に良い人のように見える人が実は裏表がひどく、裏でアカンベーとされている事もある。 そういう事が見えた友人には、当然距離を置くこととなる。 それでは、これらの事で全てが線引きされて良好な交友関係を維持できるかというと、それも分からない。 調子の良い、とっつきの良い人が全員悪人ということではない。 どこか波長が合うから、その人も愛想良いということもある。 その方は、別の人には実に不愛想で不誠実極まりないということもあるのだ。 あるいは、引っ込み思案で人見知りし控えめで内向的な方は誤解されやすいかもしれない。 人となりはすこぶる良いのに人付き合いが下手だと、接触の機会が少なくなるだろう。 でも誠実で付き合いを深めるほどに味わい深く慈愛に満ち溢れた人だと分かり、改めて感服する場合もある。 ことほど左様に、人を見る目があるという事に関して当てにならないものはない。 世の中には詐欺師集団やら、そこまで行かなくとも裏切りとか誤魔化しとかに手痛い目に合っている人が多い。 世界一治安のよい国日本と言われているが、様々な事件報道に接する機会は多いように感じる。 性善説性悪説どちらを取るかだが、性悪なのはいつの世でもいる。 気が合う・気が合わないということは大切なことで、人から見て、とんでもない輩でも気が合っている人達がいる。 蓼食う虫も好き好きと言われているように、男女間では尚更他人には分からない好みがあるのだろう。 どうやら、人を見る目というのは全く見当はずれの言葉であり、人間関係は勝手気ままで好きなように構築すれば良いもののようだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
阪神間のお嬢様 平成26年11月4日 昔から芦屋~御影にかけて住まいし私学の中高に通うお嬢様の中には、「ねたみ・ひがみ・いやみ」の3つを全く感じないまま育ち、年寄りになっても全く同様で、それらを感じない女性がいるとのこと。 「旦那さんによって変わるのでは?」 と問うと、「不思議なことに、旦那さんもそういうことには無縁な良い人が多い」 らしい。 これまた、不思議なものだ。 これらを称して、「阪神間のお嬢様」 というらしい。 古老に聞いた話ではあるが、「なるほど、そういえばそういう方がおられるな~。」 と、感じ入った次第である。 身近な後輩の奥様がそうだ。 そういうことかと、感心させられる。 人を疑ったりしない素直で清らかな性格、誠に絵に書いたような素晴らしい女性だが、果たして厳しく世知辛い昨今、騙されたりしないのだろうかと心配させられるが、それはそれでご本人も周りもしっかりとされた環境が保持されている方なのだろう。 私などは、日常のどうでも良い些細な事で夫婦喧嘩をしてしまう。 罵り合うような事はしないが、実につまらない意地の張り合いで腹を立てることがある。 空気を察知して、飼い犬も机の下の端に避難し、ジッとしている。 分かるのだろう、犬なりに・・・。 一方では、以下のようなことをゲーテが言っているよと、その患者さんが言っておられた。 「恨み (うらみ) 」は積極的な怒り・「妬み (ねたみ) は消極的な怒り」 だと。 恨みは、世代を引き継いでということも多いと聞く。 いやはや、当方無知蒙昧で恥ずかしい限り。 年齢を重ねるほど豊かな感性で古いしきたりを伝え、進取の心構えある者になりたいものだが、厄介者になるのが精々だろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
縦書きと横書き 平成26年10月1日 日本語は実にユニークな言語なのかもしれない。 縦書きも横書きも自由自在に表現可能だし、現代日本において普遍的決まり事はない。 新聞を見ると縦文字と横文字が自由自在に踊っている。 見出しはインパクトのある横文字として、本文は縦文字。大多数の新聞記事は横文字だが、中には基本横文字の新聞もある。 右開き・左開きの本がある。 小説単行本は、左開きの縦文字が基本。 絵本は右開きと左開きがあり、縦文字文章と横文字文章のものがある。 教科書はだいたい左開きのようで、参考書類も左開きが多い。 専門書も、左開きが多い。 教育・学問書は左開きになってきているのかもしれない。 英語の基本は横書きだから縦長の書籍だけのようだし、左開きだ。 日本語の縦書き文章で英語交じりとなる個所は、どう工夫しても英語は横書きだから、本を横向きにしなければ判読不能。 日本では、江戸時代までは毛筆縦書きだった。 漢字とひらがな交じりの文章は、現代人には読めないことが多い。 流麗達筆な毛筆体は読めない・書けないと情けないのだが、現代人としてはやむを得ないことだろう。 浮世絵は世界的文化遺産だが、木版画で精緻な絵を印刷していたこととなる。 浮世絵の中には毛筆体の署名や文面があるが、彫り師のテクニックも凄まじい腕前だったことが見て取れる。 明治以降の文体でも候文や漢字とカタカナ交じりの文章に遭遇することもある。 読めなくはないが難渋する。昔の人々は偉かったと思う反面、当時としての教養人にとっては当たり前のことだったのだろう。 現代では若者文化で理解しにくい言葉が散見されるが、それもやがて当たり前の時代になる。 時代の流れと共に言葉遣いも変化し、文体も今とは異なったものとして定着する。 パソコンが普及し、横書きの時代となりつつある。 英語なら、アルファベットをそのまま打ち込めば良いが日本語は一々変換しながらセンテンスを作成する。 面倒なことが文字文化でも欧米化してきている。 仕方がないとは思うが、変換作業時間の積算は生涯の中では莫大な時間となる。 それだけ英語圏と比し、日本語は時間的ハンディがある。 それでも、昔はガリ版印刷とか写植というややこしい作業もあったのだから、便利な時代となった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
平家も源氏も秀吉も通った道 平成26年9月1日 二号線の中でも大阪神戸間は山と海に挟まれた狭小な地の為、古来より往来していた道がそのまま国道二号線として整備されたに違いない。 特に芦屋から須磨にかけてはわずか数キロ幅の土地に現在では国道二号線、国道四十三号線、阪神高速神戸線・湾岸線、JR東海道山陽線、阪急・阪神が貫く日本一過密な交通網が並行して走っている。 それゆえ、阪神淡路大震災の折には、東西を分断され、全くの孤立状態となったのが阪神地区だ。 これらの中で最も古い通りが、国道二号線。 記述によると、7世紀に整備されたとある。 ということは、その後の様々な歴史変化の渦中では重要人物が往来していたに違いない。 六甲山を避けて北側を行くことはあり得ないし、僅かに海路での交通もあったようだが、絶対的に多かったのはやはり陸路の京都~播磨を人々は頻繁に行き交ったことだろう。 そう考えると、確かに菅原道真、源義経、平家一族、足利尊氏、豊臣秀吉らも通ったことだろう。 通った証が、各地に残されている。 菅原道真公ゆかりの神社は、二号線に近いところに点在する。 網敷天満宮系の神社がそうだ。 京都から大宰府まで、ゆかりの神社がある。 足利尊氏も中国地方遠征の帰路、現在の芦屋、打出浜の戦いで敗れている。 豊臣秀吉は中国遠征、さらに中国大返しでも旧国道二号線付近を往来している。 明治維新の頃、高杉晋作はじめ長州藩の面々も通っただろう。 長州征伐では、幕府軍が大挙して国道二号を遠征したのだと思う。 大化の改新から現代まで数多くの歴史的人物が行き来したこの道の歴史的変動を記した書物は知らないが、恐らく枚挙にいとまがないほど多くの人材が同じ道を通った。 阪急電車岡本駅から南に数百メートルにJR摂津本山、さらに南400mの地点に私の診療所が二号線沿いにある。 そしてさらに南に900mに阪神電車青木駅。 つまり山から海まで2㎞弱しかない。阪神間で海山距離最短地点だ。 平坦な所はなく、勾配の度合いは違うが全体に坂だ。 二号線は比較的なだらかな場所に位置する。 何故だか知らないが、そこを阪神淡路大震災時、激震が走った。 ほとんど二号線と一致した走り方だった。 六甲道から芦屋まで震度7というとてつもない揺れが襲い、壊滅的被害にあった。 二号線もほぼ閉鎖状態で片側2車線を緊急車両だけが走り、大阪方面は避難する車で全く動かない状態が続いた。 あれから20年、大きな代償を払い今は平和な道として歩んでいる。 その地下には巨大パイプが走り多くのインフラが収まっている。 近くの公園の地下には巨大水槽があり、大震災を受けた反面、防災強靭地域となった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
昔話を聞く 平成26年8月1日 親の言うことは、聞かない場合が多い。 反抗期というものが小さい頃にあり、中高の頃に大きな反抗期を示す。 社会人となると反抗というより親離れとなり文字通り巣立っていく。 そのような親子関係が、一般的なように思う。 親から子への継承は最も強い血縁関係であり、否が応でも親子は似る。 似てはいるがコピーではないので、個性や考え方は異なり一人の人間としての尊厳が確立される。 親子喧嘩は日常的なものだし、中々親の思うように子供は素直になれないものだ。 中には素直で親には反抗しない絵にかいたような親孝行の息子娘さんもおられるようだ。 羨ましい限りだが、親のエゴを押し付ける結果になってもいけないので、最近の親は余り口うるさく子供を強制したりはしないのだろう。 暖かく見守るというと聞こえは良いが、社会人となった子供に対しては当然そういう見守り態勢が必要だ。 ただ、成長期の子供に対しては一定のルールなり社会的規範を教え込むのは親の務め。 駄目なことは駄目だし、良い事悪い事のけじめは親から教えられる。 そうは言っても、いう事を聞かないのが子供の常。 頭を抱える親御さんは多いだろう 。反抗はしていても親の背中を見て育つのも子供であり、親がしっかりとしていないと子供はよく見ているので怖い反面もある。 お爺さんお婆さんが孫に話聞かせることは割合素直に聞き入れられ、生涯の生活様式にも影響を及ぼすことが多い。 大体において親は厳しく、お爺さんお婆さんは孫に優しいものだが、このバランスが偏るとお爺さん子お婆さん子という親子関係に溝が入ることにもなりかねないので難しいものだ。 猫かわいがりするのではなく一定の距離感を保ちながら孫に昔話を聞かせ、共に遊ぶ微笑ましい一家が理想だろう。 しかし最近では核家族化が進み、お爺さんお婆さんとは離れて暮らす家族が多い。 たまに会うと言っても、盆正月ぐらいでは孫に昔話を聞かせる機会も少ないだろう。 私は両親ともにお爺さんお婆さんは早くに亡くなっており、昔話を聞いた思い出がないので、余計昔話を聞きたかったという思いが強いのかもしれない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
夏が好きだ 平成26年7月1日 誕生日の季節を好む傾向が強いと、巷では言われている。 四季の中でどこが一番好きかと今まで相当数周囲の人に聞いたことがあるが、だいたい生まれた月の周辺を好むというのは事実に近いように思う。 私は、夏が好きだ。 夏は身軽で、面倒な事が少なくなる。 クールビズによりネクタイ着用もなく軽やかだ。 寒くて身がちぢみ上がることもないし、分厚い布団や毛布に包まれず解放的に眠れる。 日本の夏の夜は寝苦しく最も嫌われる場合もあるが、エアコンさえ上手く使えば快適な温度管理が可能で、タイマー機能も併用すると何の問題もないように思う。 夏は厄介な台風シーズンでもあり、楽しみにしていた旅行も台無しになることがある。 安定した晴天が続く秋が旅行シーズンとされるのも理解出来るし、何よりも連休が多いのも秋の特徴だ。 しかし、真っ青な夏空にカンカン照りで汗が噴き出る真夏の海水浴での思い出がたくさんある方も多いだろう。 酷暑で夏バテの日々を過ごした、クーラーの無い時代を思い出してほしい。 ああ、何と怠惰でボケっとした夏の日だったことよ。 夏休みは、冬休み・春休みと比べて圧倒的に長く、丁度合間にある登校日が鬱陶しかった。 お盆を過ぎた頃からグンと近寄ってきた休みの終わりに宿題がちらつき、とうとう最後の最後の日に駆け込みで宿題を取り繕ったことも、今では懐かしい思い出。 二学期は生徒にとって大切な時期で、中間テストとか何かと行事が多い。 早く来い来いお正月とため息交じりに鼻歌を歌い、やっと迎えた冬休みはあっという間に過ぎ去り三学期へ。 こういう風に考えると、夏休みは有難かったし嬉しかったし、あまり嫌な思い出がない。 だから、夏が好きなのだろう。 そもそも、冬休みが過ぎた頃には進級試験やら受験やら何かと気がめいることが多い。 大学卒業時には歯科医師国家試験というのがあったし、子供達が大きくなると受験で冷や冷やさせられた。 春は桜が咲き、試験合格!という喜びごとの多い季節でもあるが、反面新年度の始まりでもあり、大人になると何かと大変な季節でもある。 ということで、私は夏がいまだに大好きだ。 鬱陶しい梅雨明けの日が待たれる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
自慢話・苦労話 平成26年7月2日 先輩達との会話では、昔の苦労話をよく聞かされる。 自慢話となると、しらけムードで聞き流しがち。 「若い時の苦労は買ってでもせよ!」ということわざがある。 若い頃の苦労は自分を鍛え、必ず成長につながる。 それらを経験せず楽に立ち回れば将来自分のためにならないという意味だと記されている。 だからこそ、先輩達は飲むと必ず「昔は・・・と苦労話を聞かしてくれる。 私の姉は、口を開くと説教をする。 今でも「昔は大変だった、お前はまだまだ苦労が足りないョ!」もうウンザリだ、この年になってね~・・・!? 本当に苦労は買ってでもした方が良いのだろうか? そんなことを言われなくても、それぞれの人生で目いっぱいの苦労は皆さんしておられる。 余計なお世話、ほっておいて欲しい、と姉に言えるとスッとするのだが・・・!? この齢となり心しておきたいと思うのは、若い方々にどういう話をするかということだ。 説教じみた話は幾らでも湧いて出るほどあるのだが、それでは駄目だろう。 やはり、自分の経験で楽しかったこと、嬉しかったことをさりげなく話すようにしたいものだ。 小さい頃はどんな遊びをしていたのか、高度成長期どれほど海川空が汚れていたか、そして今こんなに綺麗な空気になったプロセスについて。 昔は蒸気機関車が走っていたし、1等車というものがあった。 最後尾車両には展望車というのがあって、そこで手を振る力道山を見たという自慢話。 当時の駅弁は停車駅の僅かな時間に売り子が「弁当~弁当~・・・」と車窓の前を行き交い、大急ぎで買ったこと。 その時のお茶は信楽焼きの茶瓶で蓋に茶を注いて飲んだ、とか懐かしい思い出がたくさんある。 童謡で歌われている世界が一面広がっていた子供の頃、夕焼け小焼けの世界・春の小川の光景、今では経験不可能なことを若い人達もきっと聞きたいのではないだろうか? 自慢話・苦労話は少しぐらい周りの者も聞いておいた方が良いかもしれない。 特に自慢話の際、年配者は生き生きとする。趣味の事は特に誰も聞いてくれない。 幾ら、「一芸に秀でる・芸は身を助ける」と言っても、所詮趣味は趣味。 玄人はお金をいただいているのだから、全く違うということだ。 それこそ苦労に苦労を重ねてお金を生むようになられて生活を営んでおられる。 素人は逆にお金を払ってアピールして人寄せを行う。 アスリートもいっしょで、プロになるには並外れた努力と精神力そして素質・運が必要で、中々楽しみながらのスポーツという訳にはいかない。 素人くさいものでも高齢者の楽しみに接することが、これからの少子高齢時代の課題ではないか。そして何よりも古来からの伝統や風習、言い伝えを聞いておくことは若い世代にとっての宝物だとも思う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
医療費は公定価格 平成26年5月1日 日本の医療は、国民皆保険制度で守られた世界最強の充実した安心出来るものだとされている。 その通りだが、医療費の支払いに関しては診療報酬点数制度という極めて特殊なもので成り立っている。 報酬という言葉自体が、あまり世の中では使われなくなっている。 また、その報酬は1点10円という符号のようなもので構築され、全国どこでもいつでも誰でも同じ金額で診療されている。 いわば公定価格での診療であり、今の日本では公定価格というものは他には無いだろう。 公的年金というような言葉の響きを持つ公定価格による診療報酬、良い意味で国民も医療従事者も守られていると言える。 反面、無駄な医療費もあるのではないかという議論が常になされている。この辺のニュアンスが微妙であり、有益と無駄との線引きが不可能なのが医療でもある。 公定価格ということは国が統制している訳で、何から何まで国の企画で医療全体が運用されている。 だからこそ昨日まで認められていた医療が今日からは駄目ですよということも再々ある。 規制ということが経済発展を阻害しているという論議が多い。 規制改革花盛りの世の中だが、医療に関しては規制そのものであり、極めて特殊な状況であるという事を国民が考える事はないと思う。 しかし50年スパンで今後の医療の在り方を考える時に、このまま推移するのかどうかは甚だ不安要素がある。 社会福祉全体では、少子高齢化を10年刻みで予測に基づいた政策を考えて行く必要がある。 2025年に、高齢者数のピークを迎えると考えられている。 さらに、2050年には人口が3割も減少する。 そのような予測通りになった時に、現状医療の供給体制で果たして良いのだろうか? 規制し続けるということは、国が明確な責任を示し続けることでもある。 公定価格堅持が国民皆保険の大原則だ。医療人としての公的責任は重いし、昔ながらの医療に関わる慈しみを持ち続け日本ならではの医療が展開して行くことを切望したい。 ただ、医は仁術という前に医療人も衣食足りて礼節を知るという状況を政府も真摯に考えていただきたいものだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
幼い頃の思い出 平成26年4月1日 私は、昭和22年生まれの団塊世代一期生だ。 小学生の頃と言っても6年間という長い期間の思い出はあまり鮮明ではなく、高学年となるほど様々なことが思い出される。 1年生の頃は、まだ蒸気機関車だった。 テレビは皇太子ご成婚の際に我が家に来た(昭和34年)。それまでは、ラジオで笛吹童子とかを聞いていた。 小学校の周囲には田んぼが多くあり、課外授業で田んぼに入り、稲をわけてもらい夏休みの宿題として鉢植えの稲を育てた記憶がある。 学校の廊下を、定期的に生徒が油引きをしていた。 除虫薬の「まくり」という大釜で煮詰めたものを飲まされていた。 それが何ともいえぬ臭さとまずさで閉口した。 遊びと言えば鬼ごっこやチャンバラごっこで、空き地や山へ出かけては夕方までほっつき遊んでいた。 これぐらいの事しか覚えていない。 中学生となると記憶量がぐんと増える。 一番は何といっても人数が多く、17クラスぐらいで900名を越えていた。 何をしても目立つことなく、先生たちも怖かった。 今と違ってビンタなど当たり前。 出席簿で頭をバシッと叩かれ運動場何周と命じられた同級生がおり一同震え上がったこともある。 修学旅行は四国だったが人数が多いので関西汽船一隻借り上げで到着後のバス車列には白バイ先導だったことが誇らしかった。 要するに危険回避のための警察の配慮だったのだが、それだけの大人数をどのように引率されたのか先生方のご苦労が今となって有難い。 当時は終戦後10年余であり、授業中脱線してよく戦時中の話を聞かされた。 神戸空集の時には山手に避難して焼夷弾が落ちてくるのを見ていた。 焼夷弾は落下時、束ねの輪が外れてバラバラと落ちて来る。 それが家屋に当たり火の手があがる・・・。 数学の名物教師は、休み時間クラシックピアノをよく奏でられていた。 ゼロ戦パイロットで空母着艦のフックを出すタイミングの難しさとか、夜間海面ギリギリでの飛行がいかに困難なものだったとかを聞かされた。 どういう訳か、こういう事は覚えているもので、授業内容など全く記憶に無い。 義務教育である小中学校は、極めて大切な期間だ。 団塊世代の数の多さは、競争ということに焦点があわされがち。 実は校舎はプレハブ造成だし、先生方も少ない人数で中々生徒に目が行き届かなかったかもしれない。 団塊世代は、ほったらかし世代だったと言えるのかもしれない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
見る・聞く・しゃべる 平成26年3月1日 日常生活において、「見る・聞く・しゃべる」ということが基本となっている。 ところが、高齢者の場合、一日中テレビを見て過ごされる方が多いように感じる。 「しゃべる」 には相手が必要だが、家族内で別段しゃべるような話題は少ない。 自らの意思で相手としゃべる事は大切だが、次第に高齢者の話し相手は少なくなる。 見て聞くだけのテレビだけでは刺激が少なすぎる。 やはり、しゃべり相手が必要だ。 知らない人としゃべる訳にはいかないが、その点、お医者さんとはしゃべる事が出来る。 多忙な先生方は限られた時間であっても懸命に患者さんと話をする。 先生への訴えを適格に伝えるのは重要。 やり取りの中で体の不調を適切に治療してもらえる。 重篤な病気ではなくても、お医者さんと常日頃から接触しておくのは高齢者にとって非常に大切だと思うのだが、医療費削減策により受診機会が少くなる傾向がある。 窓口負担金が発生するので、そうそう気軽にお医者さんにも行けないという方もおられる。 昔は、待合室が社交場のような診療所もあった。 何しろ、受付でもしゃべらないといけないし、声を出す機会として最適な場所が町のお医者さん。 受け答えに確実性が求められるし、自分の判断で治療内容が変わることもある。 そういう効用が病気そのもの以外に診療所にあった。 もう少し気楽に受診出来るシステムにならないものだろうか。 絵でも音楽でも俳句でも何でもそうだが、自分で描いて歌っても、それを聞いて評価する相手がいないことには表現をしたとは言えない。 日記ではないので表現をするということは必ず相手が必要となる。 お年寄りをターゲットとした詐欺が横行している昨今、知らない人との接触は避けないと、とんでもない事件にも巻き込まれる危険性があるので、その点だけは要注意。 「見ざる 聞かざる 言わざる」 という諺があるが、高齢者には無用の言葉だろう。 自然に目も耳も弱ってくるし、話しをする機会も少なくなる。 可能な限り人との接触を多くする機会を社会全体で作るために、かかりつけ医への定期的受診をお勧めしたい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
寒い冬 平成26年2月1日 冬が大好きという方もおられるが、私は大嫌い。 体が縮こまり、活発ではなくなる。 寒ければ着込めば良いが、暑ければ裸以上に脱げないから夏は嫌いという方もおられる。 私は冬にあまり良い思い出がない。 インフルエンザも怖いし、風邪もひく、自分の時以上に子供達の受験ではハラハラドキドキさせられた。 子供のころは火鉢ぐらいしか暖はなかった。 こたつも火を入れるのが大変だった。 豆炭を熾し足元の器具に入れておくと1日中暖かい。 夜は湯たんぽを使うこともあった。 とにかく冬の寒さをしのぐ工夫が大変だった記憶がある。 教室には勿論火の気はない。 木造の校舎で先生方もさぞ苦労なさったのだろう。 夏の暑さはどうしたか? クーラーが無い時代だから、日中はとにかくデレーとしていた。 大人たちも今ほど多忙ではないので余り仕事はしていなかったように思う。 氷は売っていたので、冷たいものばかり飲む。 従って、お腹の具合もよろしくなく食欲もなくなり、いわゆる夏バテとなる。 こういう意味からは夏のほうが過酷だったのかもしれない。 兼好法師も家は夏向きに限ると言われているのはそのせいだろう。 こういう訳で夏休みの方が冬休みより遥かに長いのだろう。 休みが長い夏が好きなのは、ただ私が怠慢を好む性かもしれない。 とにかく寒い冬が嫌いだ。 そういう私でも学生時代はスキーに行っていた。 運動音痴だが、それなりに楽しんでいた。 アフタースキーが好きだったのかもしれない。 夜間にゲレンデをトーチ掲げてストックなしの集団で滑り降りる幻想的な風景を楽しまれた方もおられるだろう。 誘われたが自信がないので断った。 友は勇敢にも参加した。 光が円弧を描きゲレンデを下りてくる。 するとポツンとある個所で火か消えた。 友が転んだのだ。 ある時、4人の友とスキー・リュックを担いで長野まで出かけた。 目的地のプラットホームに降り立つと周囲には全く雪が見られない。 ゲレンデも閉鎖。 仕方なく、なけなしの金をはたいてタクシーでさらに山奥に移動。 やっとの思いで一面銀世界に到着。 荷物を降ろすとリュックが一つ足りない。 あの雪のない駅のベンチに忘れてきたのだ。 泣きの涙で空のタクシーでリュックを届けてもらった。 大幅な出費に一同茫然。 宿から皆で手分けし、親に「すぐ金送れ!」と電報。 それ以来、冬が大嫌いとなった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ケセラセラ 平成26年1月6日 年配の方なら誰でもが知っている歌ケセラセラ。 子供の頃よく流れていた。
ペギー葉山が歌っていた歌詞を思い出す。 ずっと口ずさんでいたので覚えている。 歌詞の意味を今となって読んでみると、結構深い子供心が描写されており、母が子供に言って聞かせる状況が浮かんでくる。 「私綺麗になるのかな~、お金持ちになるのかな~!?」 「先のことなど分からないわ、なるようになるのよ!ケセラセラ」・・・ケセラセラという言葉が分からないが、何となくカラカラと笑い微笑む慈愛に満ちた母の姿のようでもある。 随分と刹那的であり、場当たり的で余りよろしくない歌詞のように思えるが、実は大変意味深長で哲学的とも言える母の受け答えではないかと考えさせられる。 今時、ケセラセラと笑い飛ばせる親はそうそう多くいないだろう。 深謀遠慮、先を見据えての習いごとにお受験に没頭する親子の姿ばかり目につく。 世の中の風潮だから抗うことが出来ないことはよく理解できる。 でもなお、ケセラセラと笑う親の姿には宝が詰まっているように思えて仕方がない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
体に良いこと悪いこと 平成25年12月2日 生まれてこのかた、体に良いことだけを目標に生きている方は、ほとんどおられないでしょう。 体に良いとされる学説も、時代と共に変わってきています。 当時は良いとされていたことも、今では良くないと言われることも多々あるようです。 そもそも、受胎した母体において母親がどのような生活様式だったのかもよく分からないことですし、誕生してからも体に良いこととは真逆の生活をしていたかもしれません。 戦後、全国民は食べるという事を第一義として生き抜きましたね。 高度成長を迎えて以降は飽食の時代とも言われ、過食に気遣いするようになりました。 そして今日では、食の安全が俄然クローズアップされる時代。 健康的生活には、適度の運動とバランス良い食事を適切な量食べることとされています。 勿論、節酒・禁煙が前提です。 しかし、これらを厳密に守った生活は味気なくなることを皆さん実体験として感じておられるように思います。 体に良いとされている事も自然体であれば良いのですが、無理に、しかも急激に行うと大きなストレスとなることでしょう。 私の義理の父は今年満90歳になりますが、お世辞にも体に良いことはしていません。 ものすごく塩辛いもの・極端に甘いものばかり食べています。 美味しいお饅頭に「甘くない!」と言って砂糖をかけて食べます。 家族は皆、父の通りに食べていたら体を壊すと別味にしております。 とにかくマイペースで余り気遣いをしない人です。 どうやら健康長寿の人は我儘で思い通りに生きて行くことがヒントなのではないでしょうか? そういえば、私の実母も思い通り生きました。 運動らしいことは皆無、自分の好きな物だけを食べ、行きたいところへ行き、勝手気ままに94歳で逝きました。 天寿全うといってもよろしいのではないでしょうか。 身内だけの情報分析ですが、ストレスを抱えないことが健康寿命延伸に関連性があるように感じています。 年を重ねるほど環境適応力の幅が狭くなるようですが、換言すると融通性に乏しくなり、視野が狭くなり、気難しく我儘になりがちとなります。 しかし、ストレスを大きく感じない人は、年寄特有のものではなく、若い頃からそうだと言う点が特質すべき点でしょう。 体に悪いことは良いことの裏返しではなく、適度に悪い事であっても精神状態が安定していれば結構長生きするものかもしれません。 とかくクヨクヨしながら遠慮がちに人目を気にし、且つまた、体に良い事を心がけなければと強迫観念を背負いながら生きている標準的な日本人は、少々考え直した方が良いのかもしれません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
時代の継承 平成25年11月1日 継承しなければならない事は数多くあるがせいぜい50年ぐらいでの活動しか許されていない我々にとって、伝えていくことの可能なことは限られている。 当然、数代継承するべき事と、その時点で完結することは明確に分けなくてはならない。 「継続は力なり」ということわざが当たり前になっているが、それはその人の人生の中での継続的努力を指している。その瞬間が大切なことも多い。 野球をスポーツ文化として継承していくことは大切だが、試合の勝ち負けというその瞬間の大事なことと文化として次世代に伝えていくことは次元が異なるのと同じだろう。 わたくしたちは多くの事象は存在しているが故に検証可能だということを本能的に感じている。 ほんの50年ほどの活動期間中に、その成果を確認したいと思うのが自然だ。 だから物事の評価は結構早い段階で分るようなものに特化されやすい。 古典芸能や伝統工芸は継承していくことに大きな意味がある。 しかし、大多数の一般人は生きている間に確認したいという衝動に駆られるのが普通だ。だからこそ、2020東京オリンピックを見てみたい、オリンピック開催の日本に身を置きたいという時空的目標を持つ人が大勢いる。 大変有意義な目標だと思う。人は自身の人生での完結型結果を望んでいる。子供達に継承することだけを目標に生きる時代ではなくなった。政治の世界でも100年の計とよく言われるが、それはたとえ話であり、現実は数年先のことでさえ政治的に不明なことばかり。 問題は継承して行く時知識の継承とある程度の経験的な内容を、どのように分類して消化吸収するかにかかっている。 教科書等による知識は、過去の知識を凝縮したものであり、概ね現代における標準的教養とされる。 デジタル化の時代となり、知識の吸収整理は随分と楽になった。 100年後には思いもかけない時代が待っているのだろう。 デジタル化という演算能力の飛躍的向上と情報収集の利便性によって、情報は今までとは比較にならない進歩を遂げる可能性がある。 社会人スタート時点では自分の知識集積により進むべき道が決められて行く。 過去の膨大な知的集積物の全てを頭に残すことは不可能であり、そのエッセンスを時代の経過に伴うものとして個人的に整理し吸収する。 そして、何十年か個人的に努力を重ねて人生は終わる。 例えば私の天職である歯科医師という職業だけを考えてみると、大学卒業から研修、医局生活、そして開業という一連の流れの中で、知識と経験との集積にともない頭の中と指先の動きが一体となり、喜んでいただける医療提供が可能となる。 技量がピークを迎えればピークアウトするのも当然であり、その時には隠居の身となる。 その中で、また誰かがそれらを継承し新たな展開を行っていく。継承とは、このようにプツリプツリと断片的になりながら繋がっていくものだと思う。 繁茂した草木もやがては枯れていくが、枯れ行く頃には下草が生え継承していく下準備が始まっている。 人間も子供が育ち社会人となるころには、親も枯れ初め、やがて継承されてゆく。 そして、子供は社会的に立派に成長している。 何か不思議な継承力というか受け継ぐノウハウは無くとも社会は続くのかもしれない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
色の変遷 平成25年10月1日 NHK大河ドラマ「平将門」では、色がくすんでカラフルではなく、何か不明瞭と言うか・・・といった批判があった。美しい瀬戸内海まで、わざわざくすんだ色に加工していたとの声もある。歴史的に色というものの記述を見たことがないので、よく分からないが、昔はモノトーンで暗い色が多かったのかもしれない。 しかし平安時代の十二単は色鮮やかで、色目というのか多くの色を使った見事な装束だ。 だから、必ずしもモノトーンで暗いという世でもなかったのだろう。色染めの歴史は知らないが、恐らく色に対しては様々な歴史的変遷がある。 江戸時代の浮世絵を見ても実にカラフルだ終戦後、困窮していた時代は確かに単色が多かった。 写真はモノクロだったが、思い出の中の昭和20年代は鮮やかな色合いの服装は街中では見なかったように思う。次第に豊かになるにつれて色合いも豊富となり、世の中は明るく派手な色が増えてきた。 色を作る、色を選ぶ、色合いを愛でる歴史があるように思う。ことに日本人は渋さを好む民族でもあり、わびさびの世界にも色合いという重要な要素がある。 冠婚葬祭に代表される色使い、デザインにも日本の特性がある。悲しい色・嬉しい色・目出度い色・普段着の色と好みにも面白い社会性を見てとれる。 古色蒼然という言葉がある。「長い年月を経て、見るからに古びた趣をたたえているさま。古めかしいようす。古色は年を経た物の古びた色合い。」という辞典表記。 古い色合いがいかにも歴史を感じ、そのものが感動的である漠然とした意味合いで使われるのだろう。 古色蒼然とした山寺、お堂という風な表現。この色に対する日本人の感性はどういうことなのだろう。 古いものに対する畏敬の念とか、遥か昔から続く伝統への美意識なのかもしれない。ここで言う古色は、その昔は鮮やかな色だったということなのだろうか。 色に対して人が感じるものは、時代の文化、宗教、経済、外国交易、交流に色濃く反映されているもののようだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
動物と植物の不思議 平成25年9月2日 生き物、生物は大きく動物と植物に分類される。 植物の歴史の方が古いらしい。 植物は二酸化炭素と水と光で、いわゆる光合成を行い酸素と糖類を産生する。 これが植物の不思議。糖類はでん粉となり、米やイモ類として我々の生きる術を決定づけている。 このメカニズムを解明し人工光合成の研究が盛んに行われていると聞く。 動物は酸素を取り込み、二酸化炭素を吐き出す。 植物と動物の共生関係には皆納得させられる。 動物は植物のように糖類という副産物を生まないが食物連鎖では有機物として植物に影響を与えている。 動物は口のある生物と言われているように、消化管を持ち、食べて消化吸収を行い排泄し、呼吸で酸素を取り込み、二酸化炭素を排出するという循環で生きている。 我々と深い関係のある植物だが、意外にも細菌は植物であり、細胞壁を有することで我々の体の細胞とは異なる。 ペニシリンという抗菌薬はこの細胞壁合成の阻害作用があるので、我々の体の細胞を傷つけずに細菌だけを選択的にやっつけてくれる。 抗菌薬はウイルスには効かないが、最近では抗ウイルス薬が色々と出て来ているのでインフルエンザ治療も以前とは格段に様変わりしている。 このウイルスという生き物は植物でも動物でもないところに分類されている。 人類との関わりでは、このウイルスと長い期間の付き合いがあり、共存関係のものもあれば、強い病原性のウイルスに今現在も苦しめられている。 このウイルスという生き物も面白い特性があり、生きた細胞の中だけで生存が可能なのだ。 宿主の動物が死に絶えればウイルスも生存できなくなる。 だからウイルスも常に変化し、宿主とうまく付き合っていくようにしようとする。 何十世代、何百世代もかけて共存関係となるウイルスもあるという。 エイズウイルスも次第にヒトとの関係で発症年が何十年何百年となれば、最早怖いウイルスではなくなり、むしろ共存してヒトの防波堤ウイルスになるのではないかという研究者もいる。 ことほど左様に、病原微生物にはまだまだ分からないことが多い。 私達ヒトも変化を続けている。 何万年スパンで考えると生き物全てが変化しているだろう。 今という時空だけを考えると解決不可能と思われる様々な問題が山積しているが、この先にどのようなことが待ち受けているのか興味は尽きない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
物事の期待感 平成25年8月1日 統計学には、確率論で期待値というものがある。 確立変数の平均値であり、賭け事の戻る見込み金などで使われるが、期待値と等しいお金が戻るというものではない。 何においても物事の結果には幾通りもの筋書きがある。 期待感が大きければ大きいほど結果は正反対になることがほとんどだ。 宝くじはその最たるもので、大きな期待感と駄目だろうという現実的な結果の2通りだけ。 統計確率論的な指標を基にくじを買う人はほとんどいない。 期待をするから裏切られることも多い。 期待感が多ければ多いほど、結果が思わしくない場合には落胆の度合いも大きい。 しかし、期待感を持たなければ人生の目標への歩みも保てないだろう。 思えば人生の中での様々な出来事で、どれほど期待をかけてきた事が多かったことだろう。 大抵は期待外れに終わることが多いのだが、そこで又、軌道修正を行いながら歩を進める。 人々は何に期待をしているのか、例えば現今のアベノミクスでは経済の上向きへの期待感が強く、その気により実際に経済は上向いているという。 日本的・世界的経済の事はよく分からないが、気というものでそれほど違うものなのだろうか。 昔から、「病は気から」とも言う。 日常的に気持ちが入らないとか、その気にならないということも経験する。 体調にもよるのだが、気がめいるという状況は、物事が上手く進まない結果において出現する気かもしれない。 気合いをいれるという時は、日常的な動作において慎重かつ心を込めて集中した状況を言う。 期待感が芽生えるのは思春期を過ぎた頃からで、老齢期まで続く。 受験・恋愛・仕事・人間関係・家庭・子供・お金・健康・趣味・孫・老後資金・老後の健康というふうに期待感も移り流れて行く。 これらの一般的期待感の内容に裏切られたことのない人はいないだろう。 期待通りに行かないのが人生だと誰しも思う。 それでも人は期待を持ちながら生きて行く。 それで良いのだと思う。 時に安んじて順にる - 荘子 - |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
予後の判定 平成25年7月1日 予後の判定という言葉は一般的ではない専門用語かもしれない。 将来予測と言えば未来学者や、はたまた易者のような感覚に浸る方もおられるかもしれない。 先のことは分からない、と言うのが正しい表現だろう。 しかし、医療の分野では、ある程度の予測が立たないと治療が進まないし、同意も得られない。 病気の治療などの経過または終末について、医学的に予測することを予後の判定と言う。我々医療者は患者さんの疾病に対して、常に予後の判定を考えながら診療を進めている。 歯科でいえば、初期の虫歯治療の場合には予後良好と判断する。少し複雑な病状の時には予後不良かもしれない旨を伝えながら治療に専念する。 予後不良につき抜歯せざるを得ないケースでも、何とか残して欲しいと望まれる時には頭を抱えてしまう。急性症状が落ち着くと、往々にして抜歯は避けて欲しいと訴えられる場合が多いが、実は抜歯のタイミングは急性炎症が消退した時こそ、抜歯後の経過が良好で済む。 どうしても残して欲しいとの要望が強い場合は、今後起こるかもしれないあらゆる状況を理解していただいた上で経過観察に入るが、多くの場合、残念ながら良好な経過とはならない場合がほとんどだ。 このように、予後の判定は歯科医にとって疾病治療の大原則であり、先の見通しを説明出来なければ治療を進める事は困難だ。 しかしながら、将来を予測するのも極めて困難なことであり、その方の生活習慣・噛み合わせの力や体質や様々な要因が複雑に絡んでくるので、はっきりとした予後判定は難しい。せいぜい5年後ぐらいを予測しながら治療を進めるが、早期治療の重要性が大切であり、定期的受診により相当数の歯は保存可能となるケースがある。 高齢化が進む現代において、90歳を超えても御自身の歯で美味しく食事をなさっている方も多い。何十年も診療を続けていると、私自身も年をとったが、患者さんはさらに高齢者が多い。従って何十年来のお付き合いの方がたくさん元気で通院されている現状に、嬉しく有難いことと喜びながら日々の診療を続けている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
極楽飯 平成25年6月1日 晩の極楽飯、朝の地獄飯を食べて立つ : 種田山頭火 山頭火の日記の中に、世間師との会話がある。晩の極楽飯・朝の地獄飯という言葉を聞き面白く思ったと記されている。 世間師とは、 世間に通じていて巧みに世を渡ること・悪賢く世を渡ること・また、その人・ 旅から旅を渡り歩いて世渡りをする人のことをいう。 極楽飯という表現があることを知り驚かされた。 80年も前の行乞の俳人 種田山頭火のこの句は、現代社会にぴたりと当てはまる。 慌ただしく、あたふたとした身支度時、朝食のパンを頬張り飲物で飲み下す。今日が良き日となるように祈る余裕もなく、嫌々登校・出勤の朝の食事。現代社会において、仕事を控えた朝が楽しくて仕方ない人は珍しい。 何とはなしに嫌気がする朝を迎え、仕事が終わると幾分晴れやかとなる。週末ともなるとうきうきとし、週初めは淀んだ空気のごとく倦怠感に浸ったまま仕事に就く。その繰り返しの人生でもある。 放浪の詩人山頭火は、法衣に包まれた身を無理やりにでも朝から行乞に出、疲れ切った体で湯につかり酒を飲み飯を食い、同宿の者と会話をし、寝る。その間に、句を詠み日記をつける。 そしてあくる日も、優れぬ体調を押して、また立っていく。 その繰り返しだ。その苦悶の人生の中に、感性豊かな俳句を詠み、後世の人々に感銘を与えている。さらにまた、山頭火は「人生で最も大切なことは、良い寝床と旨い飯だ」とも言っている。 決して、旨い酒とは述べていない。山頭火が言うと、なるほどと思ってしまう。食事の有難さというより、人生は食って寝ることが最も重要なことだと言いながら、人生の悲哀、家族愛、思考の深さ、遊びの大切さと自制不可能な弱さを表現しようとしている。 山頭火の素顔を現す興味深い表現が残っている。 ――― 昨夜飲みすごしたおかげで、今日はだるくてねむくて閉口した、そのためでもあるまいけれど、犬に咬みつかれた、シヤレた奴で傷づかない程度で咬みついたのである、一つ懲らしめのために殴つてやらうと思つて杖をふりあげたがやりそこなつた(飼主の床屋さんは責任廻避のために飼主ではないと解りすぎる嘘をいつてゐる、犬よりも犬の主人の方が下等だ!)。」 ――― このような感性を受け継ぐ日本人は、これからも山頭火を忘れないだろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
対面販売 平成25年5月1日 昔は、市場で皆買い物をした。 「奥さん、今日は○○が安いよ!」 「今日は何がお勧め!?」 このような具合に、対面での買い物だった。 否応なく、店員さんとの最低限の会話が必要。 最近では、スーパー・コンビニで、商品について店員さんとやり取りする機会はほとんどない。 それよりも、なにも会話をしないで買い物が出来る便利さが求められている。 駅では、「○○まで大人一枚・・・」とか告げてお金を払い、改札で切符を切り駅に入る。 切符を切るという言葉は、すでに使われなくなって久しい。 書店では会話をしないが、全体を眺め、平積みの単行本の売れ筋とかを自然とチェックしていた。 話題の本や雑誌の立ち読みや、本屋での思い出は数限りがない。 最近では、ネット販売で大変便利に本の購入が可能となった。なにしろ自分の好みの本が自動的に紹介されて来る。 ある意味、すごい時代となった。 さて我々の歯科医療では、必ず対面しながら患者さんと会話をする。 話をしないと、診療自体が成り立たない。 訴えを始め、説明同意、治療の経過説明、今日の具合を、会話の中で読み取る。 当然のことだが、こういう医療サービスに関しては無言での治療は成り立たない。 デジタル化がいくら進んでも医療の対患者では会話というアナログが絶対に必要だ。 こういう風に世の中を分析してみると、合理的なデジタル化と、昔ながらのアナログ対応に大きく二分されるのかもしれない。 広い意味で心を通わせるサービス業・話はしなくても土に海に向き合う農水産などはアナログ的かもしれない。 振り込め詐欺とかの詐欺集団は、心通わせる振りをして人をだます。そういう風に考えると、人との交わり・情というもの無くしては世は成り立たないし、詐欺師に騙されない世にしてゆこうという風土や社会的活動もまた基本は対面行動から来るものである。 話し合うという、あるいは会話というものが希薄になってきた。 顔と顔を突き合わせた話が如何に大切なことか、思い知らされる時代となった。 個と個の簡単な意思交換の機会を増やしていかねば、心通う世の中ではなくなる。 話さなければ、相手の気持ちは分からない。 意見の違いが生じるという嫌なこともあるだろうが、それでもなお話は必要。 せちがらい世情も、対面活動を活性化させると豊かな社会に展開していくのではないだろうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
犬の心 平成25年4月15日 犬に心があるかどうかわからないが、少なくとも喜怒哀楽の情はある。 お客さんがくると、喜び興奮し飛び回る。 悲しそうな顔をすることもある(そう人が感じているだけかな)。 夫婦喧嘩をしていると犬達は、じっとして様子を眺めている。 とばっちりを食らうのを避けている風にさえ見える。 留守をして帰宅時には「どこに行ってたの?寂しかったよ。帰ってきてくれて嬉しい・・・!」と体中で喜びを表現する。 賢い犬というが、賢さは人と比べれば大したことはない。 反復訓練による服従性は人より優れているだろう。 不要なことは考えないので、同じことを繰り返しても苦にならない。 学習・応用力という点でも人と比し限界がある。 しかし、犬には優れた嗅覚がある。 これは人の何千倍ともいわれ、するどい臭覚は使役犬として活用されている。 麻薬犬や警察犬に代表されるものだが、服従と忍耐力は盲導犬として優れた特性を発揮する。 まあ、犬の心を人と比較すること自体が犬にも失礼な話ではある。 犬は犬、人は人。 犬は感情表現をするから、犬にも心があるように思える。 きっと何かを感じて考えているのかもしれない。 飼い主に可愛がって欲しいという願望こそ、犬の心だろう。 我が家は現在4頭を飼育しているが、それぞれ性格が違う。 本当に、全く異なると言ってもよい。 雌のゴールデンリトリーバは、甘えん坊だ。 リードに繋いだまま外出し帰宅すると、歯をむき出し鼻にしわを寄せ、あたかも怒っているかのような顔をして、頭を下げて突進してくる。 初めは怒っているのかと思ったが、実は喜びの表現だった。 笑い顔になっているのだ。 ちぎれんばかりに尻尾を振り続け体を摺り寄せて甘えるしぐさに、思わず私の顔は緩む。 また、この子は全く鳴かない。 声が出ない子なのかと思っていたが、何かの拍子に低くワンワンと鳴いた。 可愛い女の子なのに低く響く鳴き声にびっくり。 でも、普段はまず鳴かない吠えない。 犬に心があるかどうかということよりも、人間の友として古来より長く付き合う犬。 その力は時として人を勇気づけてくれる。 我が家では子供たちが巣立った今、犬が夫婦のかすがいだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
院内感染と社会的感染 平成25年4月1日 院内感染というテーマは普遍的であるように見える。医療機関内での感染を回避することは当然の事であり、それらの底上げに国を挙げて・学会こぞって懸命に尽力している。それはそれで良い事だが、院内感染以外の感染を考えてみる必要もある。 飛沫感染や空気感染では風邪・インフルザに代表されるように学級閉鎖などが問題になる。言葉づかいとして、院内感染以外のものを社会的感染と定義すると分かりやすい。人込みではいつも風邪やインフルエンザに罹患する可能性がある。そうすると、感染症が伝播するルートとして、様々な機会があることになる。待合室などでの飛沫感染等には相当無力であり、対策も難しい面がある。 しかし、視点を変えると、全ての感染を防ぐことは不可能であることも浮かび上がってくる。いわゆる院内感染での課題は医療行為中での血流を介しての感染すなわちウイルス感染が主体であり、さらに術中の細菌感染ということを防ぐ必然性があり、それらへの対策は確立されている。 私が不思議に思うのは、社会的感染の方で、一般社会においての感染成立を放置しておいても良いのか、あるいは細菌ウイルスとの共存関係が社会にはあるので、今のままで良いというのかよく分からない。 院内感染対策というと目くじらを立てる医院もあれば、鈍感な医院もあり、日本国中均一ではないように思える。しかし大きな問題を抱えているほど不潔ではないのが日本の現状。先進国では大筋医療的清潔概念が確立され実行されている。医療機関の診療は出来るだけ清潔であらねばならないのだが、感染症全体を見据えた社会的な課題を掘り下げる必要もある。 集団免疫により天然痘蔓延時でも生存した人々がいる。歴史的には感染症で絶滅した地域もあるが、多くは集団免疫によりからくも生き延びている事例が多い。感染症と人類の未来には、まだまだ厄介なことが起きるかもしれない。 医療的清潔概念と社会的清潔概念は異なる位置づけで良い。そこを混同すると訳が分からぬ世界が待ち受けている。病院診療所の清潔保持と一般社会での清潔は明確に一線を画する問題だ。 公衆衛生概念が社会的清潔概念と等しいということにつきる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
国民皆保険制度維持への道筋 平成25年3月15日 TPP参入により、世界に冠たる我が国の国民皆保険制度崩壊の危険性を指摘する声が強い。 まだ土俵に上がってない時点での危惧ではあるが、TPP参加により国民皆保険を止めさせるという直接的動きとはならないだろう。 しかし、混合診療解禁への要望と実施への圧力は増し、結局受け入れざるを得ない状況となるかもしれない。 一部でも混合診療解禁となると、その時点から民間保険が参入し、国民皆保険はなし崩しに崩壊して行く可能性が極めて強くなる。そうなることで公的資金投入ならびに保険者支払額の減額がなされ、今で言う保険財源枯渇に終止符が打てるという魂胆が見て取れる。 昨年平成24年度の国民医療費総額は37兆円であり、その内訳は社会保険料18兆円・自己負担5兆円・公費14兆円となっている。 乱暴な言い方をすれば、互助・自助・公助という現在の医療保険の理念概念から、この比率を保険料5割・自己負担2割・公的補助3割という凡その比率配分で固定化すれば、この先も永遠に国民皆保険を堅持する制度として定着するのではないかと思われる。 すなわち、民間保険の概念とは著しく異なり、保険料のみでの運用は始めから想定せず、教育制度と同様の考え方に基づく制度運用とすれば問題なく継続可能となる。 国民皆保険とは、公的医療保険と同義語であり、相互扶助・自助・公助により成り立っている。公的扶助の負担増加に政府は一丸となり医療費抑制に血眼となっているようだ。 相互扶助という観点でも、膨れ上がる医療費に保険組合が破綻するとの悲鳴が、現状の保険者機能強化に繋がっている。 3割負担の限界による混合診療導入が目論見られているが、TPPの実質的介入を招く誘因ともなる恐れがある。 国民皆保険堅持のためには、保険料率増加・公的資金に頼るだけではなく、根本的に一定料率による国民負担の在り方が問われている。 料率固定化を法制化してしまえば、少子高齢化・人口減少にも対応可能となり、その時代にマッチした内容に変化して行くことだろう。 現状堅持には、保険という概念を取り払い、制度の統合を図り、年金制度と同様の仕組みを新たに構築する必要がある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ネットと日本社会 平成25年3月4日 阪神淡路大震災時、ネットというものは僕の周りにはなかった。 あれから18年、猛烈な勢いでパソコン環境は整備された。 震災当時、カメラはフィルムだった。 携帯電話は普及していなかったが、私は持っていたので随分助かった。 当時の携帯には、カメラ機能は付いていなかった。 震災の記録には、バカチョンカメラを使って少しだけ撮った。 今のように圧倒的な記録媒体としてデジカメが無かったのだから、震災の記録としての素人撮影の写真も東北大震災に比し圧倒的に少ない。 そもそもSNSが無かったし、ブログ・ツイッターも無かったので新聞・テレビによる情報だけだった。 ネットの功罪が巷を賑わす時代となった。 活字離れ・時間の無駄・思考停止・依存症・存在意義の片鱗さえ無し・等々、相当辛口の批判が多い。 ネット忌避感を訴える識者の意見も良く分かる。 功の部分では、デジタル化による演算能力の飛躍的向上で、様々な情報の解析はじめ検索が瞬時に可能となったこと。 家電製品・車を初めとしてデジタル化が無ければ、もう成り立たなくなった。 メディア情報もその真偽の判断を読者が選別出来る時代となり、今まで随分と特定のメディアによる洗脳的報道がなされていたことにも気づかされるようになった。 事例を挙げた功罪だが、その他も含めて時代は最早デジタル化を避けて通れない状況となっている。 否が応でも、世の中のデジタル化はさらに進化する。 ネットの世界も、衰退はおろか益々加速されたネット社会となる。 このような背景の中で、幾ら忌避感を抱いていても知らず知らずのうちに個人の中にもデジタル化とネット化は進行して行く。 だとすると、老若男女すべからく何らかの対策を講じた方が良い。 政府が進めるネット化はある意味恐ろしい内容も含まれているが、例えばパソコンを触れない高齢者には強要するのではなく、消え去るのを待っている節が覗える。 我々医療機関ではオンライン請求の義務化が進んでいるが、現在の高齢医療者にはオンライン化が免除されている。 従来通りの紙レセプトでの請求だ。 政府方針の中で、出来ないものは見放し、出来るものだけで今後の医療を構築し直す魂胆なのか? ことほど左様にデジタル化・ネット化は進行中なのだから、腹が立っても、意地でもこなす意思を見せておかねば世間に飲み込まれてしまう。 飛脚郵便・郵便手紙・電話・電報・ファックス・メールと、時代は移ってきた。 これからも思いもしない画期的な技術が出現し、それに合わせて時代は進化して行く筈だ。 そのような中で、時代の文化も育まれる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成25年2月15日 中 尾 薫 [ 険しい道のりを行く ] 兵庫県歯科医師会も、 平成25年4月から一般社団法人に移行する。政府の法人改革の一環として必要な道のりであるが、当然今までの社団法人時代と異なる点も多い。 その最たるものは、歯科医師会そのものが「公益に資する組織」として位置づけられることである。 公益性は従来から歯科医師会の主たる目的であったが、その反面、会員のための活動が制約される。 財産管理についても従来と異なる点が多い。 中でも、会長選挙は大きく変化する。法的拘束のない会員意識調査(会長予備選挙)をまず行い、最終的に6月の代議員会(現状の代議員メンバー)において新法法人として法的根拠がある理事選挙を行う。現代議員会メンバーで定数分の理事を選出し、その理事者の互選により新会長を選定するという流れになる。紳士協定により会長意識調査(予備選挙)の結果を遵守することが考えられるが、代議員会で意識調査トップのものが必ず会長(代表理事)に選ばれるとは限らない。さらに、すべての会員は一定数の代議員の推薦があれば理事選立候補が可能なので、全会員が理事に立候補可能である。このように会長選出が行われることとなるが、理事選内規・細則の取り扱いによっては、予期せぬ理事者が当選する可能性もあり、執行の混乱が生ずる可能性が残る。 総会が無くなり、最高議決機関として代議員会の権限が強まり、執行において代議員により理事会が監視されることになる。盤石な執行部が実現しないと極めて歪な理事会・代議員会運営を余儀なくされることもありうる。 一般社団法人移行期の今回の会長選出において、私自身の行動を決定する根拠は、「兵歯の安定」を目指した会員全体の協力に基づく民主制の確立である。これを会務執行の基礎とし、会員のすべての英知を総動員した全県下合意の執行部を誕生させることにある。 兵歯の未来のために、民主的に意見交換を行うことが重要であり、此の度の予備選挙の意味は会員にとって極めて重要なものと考えている。予備選挙は会長に相応しい人を会員が直接選ぶことができる唯一の機会である。 [ 思いは一つ ] 斬新なアイデアは、時として連綿と守られてきた公益に資する学術団体としての「兵庫県歯科医師会の基盤を揺るがす危険性を併せ持つ。今一度、 組織の根底を固めたうえでの、過去にとらわれない施策の執行が不可欠である。 新生兵歯は、民主的な歯科医師会を守るためにあえて会長予備選挙という会員に直接問う形をとるが、次期執行部は様々な対立を超えた会員の英知を結集した組織であることが求められる。 今、何をすべきかをしっかり意見を戦わせたうえで、全会員の意思を確認し、その後、県下が一つになる執行部の実現が急務だ。 今必要なのは、会員全員の力を一つにできる執行部の実現である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
無理なき人生の歩み 平成25年2月1日 田中角栄は、ある時、志を抱いた青年に次のようなアドバイスをしている。
そして、60%を超える国民の支持率があって何故反面教師なのかと問うと、田中はこう言ったのだそうです。
その後、田中角栄はロッキード事件で逮捕されている。 その時の青年は、今は有名な政治家となって、「無理をしたとは、こういうことなのか!」と述懐している。 無理をしない人生の歩みということを考えてみよう。 誰しも、程度の差はあれ相当無理をしてきている。 無理はしない方が良いと言われても無理はつきもの。 その人が自分の人生を振り返り、ああいう無理は無駄だったな~と感じることはあるだろう。 その時に、どのような無理を承知で遮二無二頑張ったかだが、無理だと思ってもやり遂げて無理ではなかったという事も多い筈だ。 無理かどうかは程度の問題であり、無理と感じる事は避けた方が良いと田中角栄は言っているのだろう。 全てが結果論であり、無理がたたって雲散霧消という人生もある。 結果オーライと思っていれば丁度良い。 何事も無難にという人生観は、私には似合わない。 「お前は苦労が足りない!」と、今でも姉に言われている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
また行きたいところ 平成25年1月15日 何気ない日頃の行動の中にも新鮮な出会いがある。 思わぬご厚情をいただき人生の岐路を迎えることもある。 また会う機会があるだろうと思いつつ、出会えない人もいる。 記憶の中で、お世話になった数々の方々を思い出すこともある。 心の中で感謝をしていても二度と会えない人が多い。 皆それぞれ様々な方々のお世話になりつつ人生を歩んでいる。 会って、口に出して「有難うございました!」と伝えることは無いが、心の中では有難いことだと反復して礼をしている。 あれだけ世話をしてやったのに、と思っておられる場合もあるかもしれないが、頭を下げたままでは前に進めない。 恐らくほとんどの方がそのような思いを持ちながら歩んでいる。 また行きたい・また食べてみたい、という願望を持つこともよくある。 食べ物に関しては嗜好変化で年を重ねると、また食べたいものも大きく変わる。 行きたい所も変化するが、案外再訪が叶わない場合が多い。 旅の思い出は数多くあるのだが、また行きたい所は限定してくるようだ。絶対にまたすぐに来るぞ!と思った地にいまだに行けてない所も幾つかある。 もう来ることは無いとその時思っても、何故かその地に立つ事もある。 最近はテレビで思い出の地を放送していることも度々見る。 新たな地よりも、懐かしい地の再訪を望む自分は、恐らく年を取ったためだろう。 未知の地への旅よりも心地よい思い出の地を選びたい。 年寄だと言われても、それで良いのだと思う。 爺くさいと思われようが、自分にとって心地よい旅がしてみたい。 また行きたいところというのは、特別の地でも何でもない。 自分にとっての行きたい所だ。 どうしても再訪したいと思うところは、それほど多くはないが、家内を連れて行かねばと考えている地はある。 実現しなくとも、そう思うだけで楽しい。 限られた時間軸の中で、後どれほどの旅が出来るのだろう。 好きなものを一番に食べる人・後の楽しみに残しておく人、私は早く行きたい所に飛んでいきたい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
半世紀を振り返り 平成25年1月1日 新春を寿ぎ、皆々様にとって良き年となるよう念じ上げ、年の初めに感慨深く半世 紀を振り返ってみたい。 昨秋、中学校卒後50周年同窓会が神戸の生田神社会館で催された。 卒業後初めて の同窓会。団塊世代の市立中学は17クラス870名余の卒業生。 その内、70数名が当日参加された。 懐かしい面々と言いたい所だが、さっぱり誰が誰だか分からない。 ネームプレートを付けて、各クラスごとに着座しての懇親会だったが、幾ら話を しても思い出せない。 かろうじて10名ほどが明確に思い出せた。 それもその筈、彼ら彼女らは高校が同じなのだ。 つまり、50年間全く音信不通 の者は記憶に無いということになる。 当時の卒業写真の映写をし、幹事が説明してくれるのだが、思考回路は閉じたまま。 情けないが、半世紀経つ と記憶もどうやら怪しいものとなるようだ。 皆も僕を見ながら同じことを考えていたのだろう、「この爺さん誰やったかな~!?」。 昔の事を思い出す場合、時系列により思い出深度が異なる。 誰しも、幼児期の思い出は全く無いい。 4~5歳の頃の事は、よほど稀なものは思い出す。 小学校低学年では、鮮明さに乏しいが学年が上になるにつれ先生のことなどを思い出す。 中学の頃も、先生を中心に思い出す。 高校の頃は、相当多くの思い出がある。 大学の頃のことは、昨日のように思い出す。 青春期から結婚、壮年期の 頃は、明瞭な思い出がたくさんある。 老年期に入り、皆が言うのは若かりし頃が昨日のようだと・・・。 時の流れの感じ方は若いころはゆっくり、年をゆくにつれ早くなる傾向が強い。 同じ時の流れにもかかわらず、年齢により感じ方が違うのだ。 感じ方もあるが、辛かった事は比較的多く覚えている。 反対に嬉しかった事は、そ う多くなかったようにも思う。 思い出は大切だが、さらに重要なことは今を生きる力と気持ちだろう。 しっかりと前を向き、年を重ねているからこそ可能な生き方を目指したいものだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
日常生活 のリズム 平成24年12月15日 一日の始まりは、陽が昇り、そして陽が暮れて終わる。 それが必ず365日繰り返される。 私達も太陽と共に日々を送る。幾ばくかの方は昼夜が逆転した生活を送っておられるが、恐らく大変なご苦労があるのだろう。 大部分の方々は朝起きて夜寝る間の生活のリズムを刻みながら生きている。 この生活のリズムが実に多様で、小さいころ・若いころ・壮年期・老年期では随分と異なる。 夜遅くまで活動する若いころを思い出すと、よくもまあ無茶をしたものだと考え深い。 社会人になると、定時に間に合うように朝早く起き、長時間の通勤、退社は定時で終わらず、おまけに夜な夜な飲み会、極端に少ない睡眠時間を日曜日に取り戻そうとお昼近くまで泥のように眠り込む。こんな毎日が、その人のリズムになっている。 朝の目覚めが良い人は人生得な生き方が出来るように思う。眠れない・起きにくいなど、人それぞれだが、そういう身体的特性も人の日常リズムであり、そう簡単には変えられるものではない。 もう少し掘り下げて、一日を振り返ってみよう。 朝起きて歯を磨き・顔を洗う。 朝食をとる、トイレをする、着替えて出かける。このひと時をとっても、人それぞれ随分と異なる筈だ。 しかも、その人にとって、時間も含めて全てがリズミカルに進まなければならない。 仮に何かの拍子に朝食をとらずに大慌てで出かけるとすると、一日中リズムが狂うかもしれない。 全てにおいて個人の日常リズムは固定されている。そのリズムが狂うとどうも体調も良くなくなる。 ところが、年代の経過とともに、その環境においてリズムも少しずつ変わってくる。定年退職を迎えると、たちまち生活のリズムは大きく変化する。 無理が出来る人は羨ましいが、かといって自分が思っているほどその方は無理をしてないのかもしれない。 人それぞれの生活のリズムがあって、全ての日本人の一日が回っている。 リズム正しく生活する事が、特に高齢者にとっては、大変重要な健康維持の柱だと思うのだが、どうだろう? |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
時代の流れ 平成24年12月1日 去る昔、後輩の診療所を訪ねたことがあった。 その際、何気なく設置されていたパソコンが視野に入った。 画面の写真がクリクリと変わっている様を見、「これ何!?」。いわゆるスクリーン・セーバーのスライドショーだったのだ。 その驚きは鮮明に覚えている。今となっては、どうってことのない事なのだが、すぐに友に質問をし、パソコン(Windows 98?)というものに興味深く取り組んだ。 かれこれ10数年前のたわいもない出来事だ。 IT化と言われて久しいが、これほど社会に浸透し、産業革命以来の革命的アイテムになるとは想像も出来なかった。 その友には感謝をしている。 きっかけはどこに転がっているか分からないし、つまずいた石を拾い上げて投げ捨てるか、持ち帰って磨き上げてみるかは人によって、また、そのつまずき方によっても異なる。 我々の年代になると、パソコンは実に面倒なものだし、必要性からみても、それほど重要なものとは思えないかもしれない。 ああいうものに振り回されるのは良くないと言われる同輩も多い。 だがしかし、時代の流れというものはそういうものだろう。 現実に医療費請求のレセプトというものもデジタル化された。 年齢区切りで、私より1歳年上の先生は紙による従来型請求で可とされている。 私はカルテも電子化したが、これがまたものすごく面倒なもので、手書きの方がよほど効率が良い。これほどパソコンに慣れていても、電子カルテはややこしい。 でも、確実にデジタル化の波は、業種にかかわらず押し寄せ、紙媒体なかんずく手書きによる処理は消えて行く運命のように感ずる。 好むと好まざるに関わらず、時代は流れ変化して行く。 流行りを追いかける軽薄な輩と切って捨てるのではなく、時勢を読み、冷静沈着にチャレンジする気持ちを忘れてはならない。 常に好奇心旺盛に興味を抱き、一瞬一瞬を見つめ、且つ少し先を読むようにしたいものだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
労働力人口 平成24年11月16日 2010年国勢調査を基に2012年9月15日に労働力調査が総務省より公表された。それによると、人口動態として、65歳以上3000万人・70歳以上2256万人・75歳以上1517万人・80歳以上893万人。就労者は65歳以上で544万人(男性333万人)という結果であった。15歳以上の就労人口は6630万人とされており、65歳以上が約1割弱である。 今後の推計では高齢者が増加し、少子化の影響で労働人口は減少するだろうと言われている。普通に考えると、高齢者就労人口を増やせば良いように思われるが、どうなのだろう。私を含めて少なくとも前期高齢者の自立のためにも高齢者就労雇用機会を増加させていただきたいものだ。 私は歯科開業医で定年制はないが、様々な状態から高齢歯科医は自然と診療の機会が少なくなるもので、定年制が無いからといって、若い方と同様バリバリと働ける訳ではない。しかし、老練ということは知識・経験に裏付けられた独特の医療対応が可能だとも言える。大きな手術や込み入った複雑な治療が困難となっても、基本的治療・診断や相談事や様々な医療分野で有益な社会的貢献が可能だ。 医療環境はさらに拡大して行くだろうが、完全な内需産業とも言える医療の今後を国民の皆様も十分理解いただき、適切な広がりを期待したい。GDP比での医療費の上限がどれぐらいが至適なのか、様々議論があるが、衣食住を度外視した医療費の拡大は望ましいことではない。 しかし、現状の医療費総額は先進各国と比しても低水準であり、まだまだ今後充実した医療環境の整備が望まれる。当然、雇用の機会は増加する。そもそも医療を聖職として、お金がかかるのは悪・医療費削減こそ国家的大命題だというロジックから抜け出し、医療は広い意味での産業であり、それらの産業を充実させれば雇用の機会が増大し、内需拡大にも貢献するという論点に基づいた政策展開が是非とも必要だ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
クラーク博士 平成24年11月1日 「少年よ 大志を抱け!」という名言は誰でも知っている。
クラーク博士(1826~1886)が札幌農学校を去り行く時に馬上から校生に発した言葉とされている。 "Boys, be ambitious like this old man" と述べたとも言われている。 この時クラーク博士は齢50。 私は65歳だから、"very old man"ということになる。 サムエル・ウルマンは、青春という詩で「青春とは人生のある期間ではなく、心の持ちかたを言う。・・・歳月は皮膚にしわを増すが、熱情は失えば心はしぼむ。・・・・」と謳っている。 クラーク博士の時代の平均寿命は50歳ぐらいだった。 平安時代では30歳とも言われている。 現代の感覚では考えられない短命の人生の中、人々は人生の知恵を凝縮させて生きたのだろう。 今は長寿社会になったが、老化と言う意味・中身は昔も今も大して変わらない筈だ。 例えば写真というものの比較では、100年以上前と現在の写真比較は困難。 自分の家族でも、せいぜい曾祖父母時代の写真が残っているだけで、それ以前の先祖がどのような顔立ちだったのか、人となりは?さっぱり分からない。 よほどの名家や歴史上の人物なら、伝聞や古文書等で判明するかもしれない。 病の歴史には詳しくないが、長命が故の歴史的人物は多い。 徳川家康もその一人だが、野心家にとって長生きは大きな目的成就の要因だったのだろう。 想像だが、昔は元気な老人は少ないために尊ばれ、若い人達に優れた習わしを教え・伝えてきたと思われる。 現代と比し、医療的には決して恵まれた環境ではなかっただろうが、知恵の伝承の大きな社会的人材だったことは確かな事実。 人生50年時代の人生リズムと現在の80年超時代とでは明らかに異なりがある。 会社の定年も60歳から65歳になりつつある。 恐らく平均寿命の人生速度比率に合わせると、そういう計算になるのかもしれない。 人生全体を100として、生まれて2割・死ぬ前の2割、合計して4割、今だと30~40年ぐらいが非生産年齢というところだろうか!? 65歳の私はクラーク博士のようにかっこ良い去り方は出来ないが、もっと現代風にスマートに活力溢れるどっしりとした老年を目指す。 且つ、若人世代に老害を撒き散らさぬよう、そして壮年期の皆さんに知恵を伝え、共に考え・検証し、生き生きとした人生を送ることが出来るように前向きな日々を送りたい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
「定年退職時歯科健診」の勧め 平成24年10月15日 2年に一度診療報酬改定が行われる。 改定直後の1年間は改定内容に沿った内容で医療費は推移する。 2年目となると、改定の影響は薄れてくる。 医科では自然増という診療報酬改定とは無関係の増収が年次統計資料に見て取れる。歯科ではこれがほぼゼロ。 その原因は様々指摘されているが、医科では70歳を過ぎたころから急に医療費が増加する傾向が強い。 超高齢化の現代において、体に不安を覚える高齢者が医療機関を受診することは至極当然のことだ。 高齢者が増加しているのだから、その分診療の機会が増え、それが自然増に繋がっているのかもしれない。 片や歯科ではどうだろう。統計によると70歳となると受診者は横ばいとなり、75歳以上となると激減する。従って歯科医療費の自然増は無いこととなる。 この社会構造的要因が医療費全体の増加が止まらない理由だろう。社会保障一体改革を叫ぶ政府もこの点をどのように考えているのか定かではない。 歯止めをかける政策は、とうてい容認不可能であることは全国民の一致した考えであることを確認しておかねば、水面下で高齢者の受診抑制施策を練っているとしたらとんでもない考え違いである。 歯科医療は生活の医療とも言われる。 口から十分に食事を出来るようにサポートする歯科医療は承知されているだろうが、受診機会が少ないことが残念に思われる。 例えば、定年退職を機会に歯とお口の状態チェックと治療を推奨する啓発活動があっても良い。医科的疾病により歯科治療が制限されることもある。 循環器疾患等で抜歯や麻酔がしづらい方は満足な歯科治療が進められない場合もあるだろう。だからこそ定年後10年ぐらいのうちに当分歯と口の状態では困らないように歯科受診をされることをお勧めしたい。 我々歯科医療機関の増収のためではなく、安心な老後のための必須のケアーだというご理解をいただきたいものだ。歯科医院は敬遠される方が多い。 治療の音と痛みという先入観から、少々不具合があっても我慢されている方がおられるのではないだろうか。 企業戦士の間、歯科治療は後回しになりがちだ。第二の人生のスタートに際し、歯科医院の門を叩いて欲しい。生き死に問題ではないのだから、快適な老後を確保するために恐れず来院をお待ちする。 今までの運動では8020運動が歯科では最も社会認知されている。 80歳で健康な歯を20本残そうというものだ。まだまだ、この運動は展開強化されねばならない。 80歳の国民の38.3%しか達成されていないからだ。 加えて、「定年時歯科健診」が全国で実施されれば、8020運動の達成が早まることは間違いない。歯科医の自己保身ではない。 一時的に自然増に繋がっても、運動展開が充実されれば結果的に高齢者歯科受診は減少するのだから。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
危機管理の難しさ 平成24年10月1日 山本七平氏著 「日本はなぜ敗れるのか」 角川書店 2004年3月10日 初版発行本 から、以下を引用した。内容は1975~1976に執筆されたものなので、今から35年以上前の山本氏の言葉だ。戦後67年を経て、氏の論壇は全く古びていないし、むしろ驚きの感銘を受ける。 人びとは危機を叫ぶ声を小耳にはさみつつ、有形無形の組織内の組織に要請された日常業務に忙しい。そしてこの無反応を知ったとき、危機を叫ぶ者はますますその声を大にする。しかし声を大きくすればするほど、またそれがたび重なれば重なるほど、まるでイソップの「狼が来た」と言いつづけた少年の言葉のように、人びとは耳を傾けなくなる。だがそのとき、だれかが、危機から脱出する道はこれしかない、と具体的に脱出路を示し、そしてその道は実に狭く細くかつ脱出は困難をきわめ、おそらく、全員の過半数は脱出できまい、といえば、次の瞬間、いままで危機危機と叫ぶ大声に無関心・無反応だった人びとが、一斉に総毛立って、その道へ殺到する。危機というものは、常に、そのように、脱出路の提示という形でしか認識されない。(42頁) 山本氏の言葉は、どのような局面でも、民間組織や行政組織で今現在でも適用されるべき当時と同根の体質が続いていることを指摘されており、ハッとさせられる。危機というものは実に面倒で、総力上げて考えうる事全てを想定したつもりでも、その知恵が及ばない場合もある。災害列島に住む我々にとっての個人的危機管理の困難性は、地震予知どころではない難しさがある。一直線に伸びる竜巻の爪痕は、無残であり残念であり災害というより事故にあったような偶然性もある。だから何も出来ないというのではなく、いつどこでどんな厄災に襲われるかもしれないという心づもりが最低限必要と言うことだろうか。 従来の危機管理は、
という3つだろう。 ①②も大変困難な場合があるだろうが、③では、それこそ、どこかの国から攻撃されたり、テロや人災をも含めたこと。人びとが移動中に災害に巻き込まれることもあり、全国民の災害危機管理への万全の対策対応は不可能だ。阪神淡路大震災に遭遇した方が地下鉄サリン事件に巻き込まれた事例もある。神戸大水害で家を流され・大空襲で家を焼かれ・大震災で家が潰れた方のお話を伺ったことがある。幸いその方は命が助かったので、第三者に話を伝えることが出来た。 危機管理の困難性は、山本七平氏の言葉のように、今現在危機に遭遇しているかどうかさえ人びとは認識出来ないことだ。 組織として脱出経路を示すこと、すなわち日本の立ち位置と行く末を政治家は明確に示す時だろうと痛感させられる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
食材の買い物 平成24年9月15日 休みの日には時々家内の買い物に付き合わされる。スーパーマーケットでの買い物は、目当ての食材を選ぶ前に、どこのスーパーに行くかも問題だ。高級スーパーか、お買い得の所か、あるいは大量の食材が大容量で変える所か、等など目的別にその日の買いものの場所が選定される。 食へのこだわりが、あまり旺盛でない人を2人知っている。その二人の方の奥様は料理の達人で、ご相伴にあずかると思わず唸るほど美味い。どの料理も手が込んでいる。お客様のときだけなのだろうかと素朴な質問をすると、さらりと「いつもです!」とおっしゃる。なんと贅沢なことだろう。二人の共通点は、それが当たり前になっており、新聞など読みながら、ただ黙々と食べるだけ!この点は奥様方の不満のようだ。慣れとは恐ろしいものだ。私など夫婦水入らずで、鍋一杯の煮物を毎日食べさせられている。随分前に子供達は巣立っていったのに、相も変わらず大量のおかずを作る家内。嫌な顔一つしないで与えられた食を有り難く頂戴する私。この風景も我が家では当たり前、慣れるということは大切なことだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
様々な生き方 平成24年9月1日 前期高齢者となり、今までの人生を振り返って考えてみた。若い世代の皆さんに、どのようなアドバイスが出来るだろうか!?と。 簡単な答えは見つからない。 診療所の衛生士と雑談している時に、人生の先輩として偉そうに言ったことがあった。 ①健康であること②働けること ③少しずつ貯蓄をしておき、万が一のためには最低限度の保険をかけておくこと ④老後は自分が出来る限り少しでも働き年金頼みにしないこと ⑤独り身・夫婦・子供の数により人生設計が全くことなること この5つのことを伝えた。 いずれも当たり前のことだろう。しかし、そこには5つの項目に当てはまらない様々な生きざまがある。無限に近い生き方が展開する。だからこそ人生は面白いのかもしれない。簡単に言えば、この5項目が当てはまる。まずは健康で働けないといけないし、相応にコツコツと貯蓄に励み、最低限の万が一に備えた保険加入。老後は他人を当てにせず自力で生きようとする姿勢が重要だろう。 建前はこういうことだが、現実は困難なことが待ち受けているのが人生。 健康でありたいとの望みも、そうはいかない事情も生じることもあるかもしれない。働くと言っても会社が倒産し、自分のせいではない事由で働けなくこともある。男女の関係でも色々、付いたり離れたりは珍しいことではない。子供が出来ない夫婦もいるし、たくさんの子宝に恵まれる方もおられるが、その後の教育費等々で悲鳴を上げられるケースも見受けられる。 人生筋書き通りには行かないのが常だと思っておいて丁度よい。振り返って自分が今あることには、偶然の成せる業としか思えない事象の連続だった。歯科医師になったのは自分で選択したことだし、今も歯科医師を続けている。だが、その間の人生は全く想像出来なかった事ばかりだったし、これからもどうなるのか全く分からない。 計画的に人生設計をすることは若い世代では必要なことだが、どうにもならない宿命的な事も起こるかもしれない。 生きとし生けるもの、天命であろう未来が待ち受けている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
少し前と遥か昔 平成24年8月16日 記憶と言うものは意外と厄介なものだ。経験の積み重ねにより、織りなす人生が進んでいく。 少し前の記憶は割合鮮明に思い出せる。それは出来事に対してであり、昨夜何を食べたかどうかなどは大した問題ではない。 ところが自分の中での遥か昔、即ち数十年前の記憶は本の見出しぐらいしか思い出せないものだ。幼少期の頃の思い出となるとさっぱりである。つまり、断片的記憶に裏付けられた自分史というものは、長いロート状の筒のようなもので、筒の開いた部分が最近の出来事である。記憶というものは上手く出来ているなと思う。 時系列で思い出そうとしても、綺麗に並ばない。しかし、人生の転機となったことは鮮明に蘇る。一生懸命に勉強したか?→いいえ、大学には明確な目的を定めて受験したか?→いいえ、等など。振り返って思うと、歯学部に入学したら生涯歯科医師として生きていくという覚悟のようなものはなかった。専門職種を18歳ぐらいで選択することの不合理性も感じるが、人生というのは、選択した瞬間に決められてしまう宿命的なものもあるのだろう。 結局は非常に偏り狭い思考回路しかなかったように思う。自分の考えに基づいた行動理念とか哲学とかを深めて行き、先々を決めなければならない、と皆が言う。それはそうだろうが、中々理想的には行かぬ。後から後から猛反省することばかりだ。 ラッパの口から過去が見えるのなら、恥ずかしくて消え入りそうになるだろう。忘却の彼方という生理現象も素晴らしいが、反省を生かすことを忘れてはならない現実がある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
学校の先生の思い出 平成24年8月1日 昭和28年~昭和40年まで12年間公立の小中高に通った。小学生の頃のことは、まだらに記憶がおるが明確な連続性の思い出は乏しい。中学高校の頃の先生の思い出は幾つかある。 中学の数学の先生はゼロ戦パイロッだったらしく、しばしばゼロ戦のことを話しておられた。夜間海上飛行それも海面すれすれで飛ぶことが如何に難しいことか教えていただいた。空母への着艦では機体後部の着艦フックを甲板に張られたロープに引っかけて停止することも初めて聞き、はらはらドキドキとしたものだ。 しかし、戦争の話は決してされなかったことも思い出の中にある。その先生は、昼休みともなると音楽教室で一人クラシックをピアノで奏でておられた。あまりのかっこよさに私達少年達の憧れの先生だった。 ただ一点、欠点があった。痔のために教壇の椅子に斜めに座られ、いつもズボンの後ろから左手を突っ込み、お尻を押さえておられた。そんなことまで思い出として覚えておられるとは全く迷惑な話だろう。 英語の先生が、「蛇の目傘」と言いましょう! そう、ジャノメガサです。これはGeneral MacArthurを米国人の発音ではジャノメガサと聞こえるという訳です。 ある世界史の先生は、「アメリカではトーストの上にトーストほどの分厚いバターを塗って食べるらしいです。一度そういうのを食べてみたいものですね~!」と言われたことだけ覚えている。 ある現代国語の先生は「文章を書く際に、接続詞を多用せず、短く分かりやすい表現をしましょう。決して同じ言葉を何回も使ってはいけません!」と言われた。これは、今でも自分が文章を書く時のセオリーになっている。 様々な教えをいただいたが、肝心の教科の内容は全く思い出せない。しかし、成績が悪くとも自分の努力が足りないからで、先生を悪いと思ったことはない。それは自らの努力不足であると考えていたが、今思い出してもとにかく当時の先生は怖かった。先生の威厳というか、先生は尊敬も含めた聖職にある人との思いが強かった。 私はおとなしく目立たない子供で、えこひいきなどしてもらったこともないし、先生方に私の記憶を持つ方もおられないだろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
老 医 平成24年7月17日
大いなる意気込みと大望を持って開業したが、以前はあれほど多くの患者さんを診ていたのにふと気付くと最近はどうして患者が少なくなったのだろう!?そういう感慨を持って播水はこの句を詠んだのだろう。兵庫県が生んだ五十嵐播水は神戸中央市民病院(当時)院長から内科開業医として活躍する一方で、高浜虚子と出会いホトトギス派俳人としても活躍した。62歳から94歳まで現役開業医であり101歳で没した。播水ほどの偉業と長命はあまり参考にならないかもしれないが、私たち歯科医師も還暦を過ぎるころから開業医人生の晩年の過ごし方を考えておかねばならないように感じる。 全国平均での開業年齢は35歳だそうだ。50過ぎまでの15年間は馬車馬のごとく働くのが常だろう。その後10年経つと60歳還暦、さらに15年で75歳、後期高齢者と呼ばれる。平均的開業年数は分からないが、生涯現役だとしても、70歳までで35年間・75歳で40年間・80歳で45年間の開業医人生だ。人によって異なるが、この開業年数30年~40年間には様々な変化があるだろうし、社会変化も予測不能の激しさであろう。人間というものは、往々にして自分が欲する現実しか見ていない、レンズの焦点のようなものだ。何か一点に強くピントを合わせると、その問題だけがクローズアップされる。歯科医療も患者側のことは一生懸命考えるが、自分たちの老いのことに焦点を合わせる機会はほとんどない。国民にとって、老年歯科医師は大変貴重な社会財産資産であるし、その経験と知識、技術をどのように活用すれば良いのか議論が待たれる。例えば「老齢期歯科医師の最前線」のような集中講義を歯科医師会主導で開催し、これらの課題の問題提起をしても良いだろう。 団塊世代以上の年齢の歯科医師は、世間同様子育ても終わり比較的余裕がある人生を送っている。チャレンジ精神旺盛ではないが、その代わり慎重であり、自分が出来る範囲の診療を誠実にこなす。若い世代が無茶をするという意味ではない。そろりそろりと経験を生かした着実で大胆なことはしない世代となっているということだ。数も多いのだから、老練な歯科医師活用法を世間が求めれば、若い世代を脅かさないような診療形態があることを示してくれることだろう。老健施設での口腔ケア講習や各地老人クラブにおける講演などボランティア的な活動がシニア歯科医師には似合っているかもしれない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
健康志向 平成24年7月2日 世の中に健康志向が闊歩している。メタボリックシンドロームという言葉が厚労省指導下で世に定着して久しい。特に肥満は不健康とのレッテルを貼られる傾向が顕著だ。高血圧・高脂血症・高血糖…。好きなだけ飲んで食べて、その上ストレス多い生活が良くないとされている。適度な運動は欠かせないとのことで空前のジョギングブーム、ジム通いの面々も多い。週に2~3回は適度に汗をかく運動が不可欠らしい。 僕は不健康そのものの生活を送っている。先日もある内科医に「運動をしてないのですか…!?」と、驚きの表情から、次の瞬間実に気の毒そうなという顔をされた。少々お腹が出っ張ってくると、「腹出てるな~…!?」と、これまた憐れみの目で見つめられ嘆息を聞かされる。確かに健康志向に頷けることも多いが、だからといって、その枠からはみ出た者を精神的に追い詰めたり、社会的弱者のような目で見ることは止めた方が良い。 運動量というのも人により異なるだろうし、運動は即ち競争であり負けたくないという気持ちが誰しも強い。ゴルフを愛する御仁は多いし、あのハンディという絶妙なシステムがさらに面白さを助長している。しかし、テニス・水泳・マラソンなどでハンディを設けると誰もやらないだろう。各スポーツで競争をあおるようないろいろな工夫がなされている。しかし、健康のための運動は競争ではないし、プールを歩いたり、トレーニングマシーンで黙々と汗を流すこともあまり面白そうなものではない。人は競うことで歩みを速める。何事も競わないで健康に留意するということ自体がストレスになるように思えて仕方がない。 腹八分目で散歩を欠かさない日々は確かに良いだろうが、さりと「??」である。ことほど左様に自分を律することは難しい。何かと理由をつけてみずからを正当化する。わたしは頭の体操で随分とエネルギー消費していると勝手に思うようにして、さらに身勝手な日々を送る。単に怠惰なだけであるが…。生きざまには大きな幅がある。世の中が決め込むのは良くないし、文化活動でさえ、ある種権威者の声が大きく、現状の常識がかすむこともある。文筆家で、やや高齢に属する方は、パソコンを嫌う方が多い。「自分は原稿用紙に書き込むことで物を考える、ITだか何だか知らないが薄っぺらで何らの文化的価値もない」といわれる。そうだろうか?私は画面で物事を考えるのと原稿用紙で考えるのとはほぼ同じ事だと思う。若者の活字離れを憂い、文化の崩壊だと叫んでも、いろいろな考え方があるべきだし、どちらの言い分が正しいのかは評価しにくい。恐らく50年もすれば、今の若者文化が定着し、さらにその時の若者に対して今の若者は嘆くのだろう「最近の若い者ときたら…!?」。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
「Give & take」 と日本人 平成24年6月15日 「Give & take」 という言葉は現代日本人にも定着しているが、とかくドライな響きを感じる。日本では「与えられる」と「与える」は表裏一体と捉えられる表現で使われる。「Give me chocolate !!」 日本の子供達が多用した戦後進駐軍によってもたらされた英語とされる。いかにも屈辱的で嫌な思い出なので、現在に至るまで「give」という英語には抵抗感を持つ日本人は多いかもしれない。 英和辞書では「give & take」 を「互いに譲り合う」とか「公平にやり取りする」と訳している。少々日本人の持つイメージとは異なる感じを受ける。英語では一つの名詞として使うようで「もらう」ということは「与える」ことと同時進行だから「与えられるだけでは駄目ですよ」という日本流解釈ではないらしい。「互いに譲り合う」とは何と響きのよい美しい言葉だろう。つまり、肯定的に用いる言葉なのだ。 しかし一方では、「妥協」に近い意味と訳されることもあるようだ。「妥協」でもよい、つまりは譲り合う基本、たとえばその者が瞬間感じて瞬時に席を譲ろうと思う心は、実際は妥協であるかもしれないからだ。「自分も疲れているが、やはり席を譲るべき方が視野に入ったので、即座に判断して行動に移した」そういうことだろう。瞬間という時間軸の中で考え・判断し・行動するということだ。何も考えずに無意識に席を譲る行動をすることは無い。だからこそ人間らしさが光って見える。 「Give & take」 よい言葉だ。しかし我が家の子供たちには通用しないと思う。「Give & give」!! 親の物は全て自分の物と思っているようだ。まあ、それはそれでいいだろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
思考の硬直化 平成24年6月1日 人は大人になると、どうやら考え方も固定化してしまうようだ。人の話を聞く・本を読む・テレビを見る・映画を見ることを通じて私たちの周りには様々な情報が溢れているが、わたしたちはそれぞれ自分の考え方、感じ方によって初めから好みではない情報を選択しない。好きな番組を見る・好きな音楽を聴く・好きな人と行動を共にする。すべての情報に対して、全て既存の固定概念による選択という行動様式がある。 人の意見に耳を傾けるとか同意する場合もまず自分自身の価値観に限られてしまう。まず自分自身にとって居心地の良い環境に置かれていることが前提で、あえて無理に嫌な状況に向かうことはほとんど無いだろう。ある人の考え方に共鳴する時も、自由な受け入れ方をしているのではなく、自分の中で許容し得る進歩的な人の話に限っているのかもしれない。 日本人という枠の中では比較的中道的な考え方が支配しているが、その中でもひとりひとりの生き方や考え方には幅があり、生活感情感覚による各個人特有の生活圏を形成している。このように考え方は人それぞれに固定化され自分らしさを発揮しているので容易に変わることはない。皆が同意しているように思われるものでも、実は間違いや誤解ということもあり得る。原発問題が良い例だろう。あれほどの事態になるとは誰も想像しなかったのだろうか。一部の原発反対論者も想定外の事態が起こったのかもしれない。 何が正しくて何が正しくないのか、議論がかみ合わないこともよくある。しかし、論破し説得し納得させるというプロセスは政治の世界では聞かない。どこかで妥協するか数の力で押し切るかだ。一般人の場合には意見が異なる時に、どういう結果に導くのかを考えると、持論を曲げた場合は優柔不断と決めつけられるだろうし、強引に持論を曲げなければ社会性に乏しい変わり者の烙印を押されることも多い。これらの例のごとく、個人の考え方は生き様の中で固定化されていることが大部分であり、感銘を受けて生き方に変化がもたらせることは少ない。先に述べたように、ある程度齢を重ねると固定概念に捕らわれ、偉い人の話でコロリと生き方が変化することは珍しい。自ら好きな作家の本を読みふけり大きな感銘を受けることはあるが、それとて自分の行動範囲の中での受け入れである。ことほど左様に人の考えを変えるということは難しいと思っておいた方が無理はない。 しかし一方では、洗脳されるということが社会的問題となることがある。特に宗教的なものや、主義・主張・信義・信念に感銘を受けたイデオロギーだが、地下鉄サリン事件、アルカイダによるテロ、赤軍派による様々な事件などが思い出される。極端に左右に大きく振れた思想信条は社会的に受け入れられることはないし、場合によっては断罪されなければならない。ただ思想が馴染まない場合でも暴力的ではない場合には、多少の偏りを幅広く受け入れる社会でないと自由民主主義とはいえない。 幸いなことに現在の日本という国は思想信条の自由が守られている良い国家だということができる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
エネルギー問題と歯科医療 平成24年5月15日 地球温暖化問題から化石燃料の功罪が問われていたが、それに加えて原子力発電の可否に日本中が揺れている。現代社会におけるエネルギー問題はどのような実態なのか考えてみた。 戦前戦後、石炭により水を沸騰させタービンを回し電力を発生させる、もしくは直接沸騰した水を軸回転による動力源として利用する時代があった。蒸気機関車しかり蒸気船しかり。その後、より効率的高エネルギーとして石油に取ってかわった。船や飛行機は石油がないと走らないし飛ばない。原子力の船もあるが商業化されていない。まして航空機は石油なしでは構造上も飛べない。石炭が燃料では飛行機の存在そのものがあり得ない。 現在の家庭では照明・テレビ・冷蔵庫・調理器具・洗濯機・掃除機・エアコン・パソコンなど多くの電化製品で電力が使用されている。子供のころはあかりとラジオだけが各家庭にあった電化製品であった。非効率だが、家庭では昔の生活に戻ることは不都合ではあっても出来ないことではない。 産業界では家庭のような我慢だけでは済まされない。いざとなれば自前で電力を確保しなければならない。節電だけでは極めて非効率で、生産活動に没頭出来ないだろう。歯科医療においては、戦後しばらく「足踏みエンジン」という歯の切削器具が使われていた。人力でペダルを踏み続けベルト式の駆動装置により歯を削るドリルに回転を伝えて使用していた。間もなく電気式の駆動装置に代わり、昭和30年代後半に現在のエアータービン方式の高速回転切削器具が普及した。高速回転なので摩擦熱を防ぐためにノズル先より水が噴霧されて歯の切削表面が冷やされていたが、歯に対する振動は相当軽減された。もちろん電気がないとこの装置は使えない。現在では他の機器も含めてまさに電気依存の中で現代歯科医療は成り立っている。まさか足踏みエンジンに逆戻りは出来ないだろう。技工の際も、8時間連続して温めないと鋳造できないような作業過程が多く存在する。 蓄電技術は今後大きく発展していく必要がある。電力は簡単にはためられないので、いつも十分な発電能力を確保しておき需要に備えてきた。しかし現状では安価で大容量の蓄電技術開発が必要である。 日本の現在必要な総電力需要を知らないが、電力需給問題解決のため再生可能エネルギーの普及も始まったようだ。しかし現在の電力需要を賄えるにはどれほどのものが必要なのか・・・? とかく報道内容に一喜一憂するが、1億3千万人の需要とは膨大なものであり、国民全員直ちに関わりの出る問題となる。過去に電力需給は多めの供給体制を確保した上での需要だった。経済成長、生活向上に伴って必要な電力を供給してきた。大きな事業規模であり、国民の経済・国民生活の基盤であるが故、その供給体制は個人的なものではなく国家的決断と実行が必要となる。石油争奪戦争とも言える太平洋戦争も国家の意思で行われた。今の日本では国家の意思が判然としないが、ここは当然毅然とした国家戦略を描かないと、国民生活破綻をきたしかねない。何とかしっかりと道を示してもらいたいものだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
世の中すべて需給バランス 平成24年5月1日 歯科医師過剰時代に突入して久しい。私が大学を卒業した昭和47年当時は、まだまだ歯科医師が足りないため町の歯科医院には患者さんが溢れていた。その後、大学数が増えるにつれ、歯科医師数はドンドン増え続け、ついにはコンビニの数を上回る歯科医院数となり、石を投げると歯科医院に当たると揶揄される時代となった。当然、歯科医師の収入は減り、今では大学受験希望者も大幅に減るという悪循環のさなかにあるのが歯科医療の現状である。これはあくまでも歯科医師側から見た嘆きであるが、患者の立場に立つとむしろ歓迎すべき状況になったと言えるかもしれない。患者さんにとって親切丁寧比較的安価な歯科医療が提供され、歯科医院の選択も容易だろう。 むし歯は激減し、口腔衛生思想の普及により歯周病への理解も深まった。これらは、歯科医師はじめ関係各位の不断の努力の結果であり、日本にとって実に素晴らしい成果と言える蓄積された社会資産といえる。 現在、12歳児のDMF指数は1.20と小児のむし歯数は激減し、当然患者数は減少している。医療保険では歯と口腔の健康維持管理に関わる診療報酬も点数化され、歯科医師の貴重な収入源となっている。疾病を未然に防ぐという課題に歯科医療は大きくシフトしようとしている。しかしながら、これは大変難しい課題であり、疾病を未然に防ぐことには極めて困難な要素も多い。さらに、貴重な保険財源を予防に無尽蔵につぎ込む訳にはいかないので、予防が歯科医師の収入の多くを占めるということにもなっていない。やはり、罹患したむし歯や歯周病の数と歯科医師の数がバランスよく釣り合わないと歯科医師から見た需給バランスは解決したことにはならない。 在宅医療は今や国策として奨励されているが、これとて30年ほど経つと高齢者人口は減少し、在宅医療・高齢者施設等は供給過剰となる。今後も人口減少は続き、歯科医師の漸増と歯科的疾患の減少という需給のアンバランスは続く。ことほど左様に歯科医師受難の時代となった。 世の中を見渡してみると、社会活動のほとんどのものが需給バランスに影響されている。石油枯渇問題しかり・石油価格高騰しかり・物価変動するものは全て需給バランスの問題だ。足りなくなれば価格が上がる。投機的意図的に物流の流れを遮るとたちまちその価格は高騰する。原発稼働を再開する動きも「夏場電力が足りなくなる!」と様々な広報活動を展開し再開に漕ぎつけようとしている。電力が不足すると産業活性が衰え、日本の活性化を阻害すると識者は言う。一方、人口推計では次第に人口は減り、40年後には1億人の大台を割るといわれている。人口が2割も3割も減るのだから、原発も不要となるかもしれない。需給バランス予測は難しいが、安定的供給が必要なものへの対策は不可欠だし、将来過剰となるものを今からどうするべきかも考えておく必要があるだろう。さらに不足するものは何かを推測し、ある程度のロードマップを示しておかねばならないし、その手順ぐらいは準備しておきたいものだ。 需給バランス問題は、世の中のあらゆる事象において存在する厄介な問題だ。世界中で大きな問題となることも多い。最近ではリーマンショックが良い例だが、お金が介在する課題には簡単に分析できない不可解なことも数多い。日本を軸に考えると貿易収支が黒字であるべきだが、反面どこかの国は赤字かもしれない。常に利益相反する状態が存在するので、ある1点の状況を一概に良い悪いと評価できない。世の中の動きはダイナミックで、瞬時としてじっとしていない。惰性で動くことも多いので、どのような対策を講じても止めようがない経済的な動きもある。需給バランスを上手に司ることは至難であり、後の祭り的な場合が後を絶たない。「覆水盆に返らず」であっても、なおバランスよくしようとする前向きな姿勢が各自は言うに及ばず世界中で不可欠な課題だと思う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
上目線 平成24年4月14日 人間は、上目線・中目線・下目線という3種類に分けられるように思う。 無論、相手の主観的な感じ方であり、その人が与える第一印象をそのように感じるという意味だ。 決して、本人が意識的に上目線をしている訳ではないが、ふと上目線と感じる目線に出会うことがある。これは妙なことだが、よく考えると確かにそういうことを経験する。 人様に対して、自分がどういう雰囲気で接しているのか全く見当がつかないし、実際には相手を不快な気分にさせていることも多々あるのかもしれない。 事実、私に対して怖いというイメージをもたれることも多い。事実は心優しく、誠に気弱で控えめでおとなしい性格だと自認しているのだが・・・!? 上目線という言葉はあるが、中目線・下目線という言葉は存在しない。 「上目線」とは、態度が大きいとか、横柄だとか、相手を小馬鹿にしていると感じられる時に使う言葉だろう。 「下目線」は強いていうなら、へりくだった気弱なイメージで、「中目線」はその中間、と勝手に私が考えた造語だ。 そのように考えると、世の中には、上目線の人が意外と多い。育った環境や置かれた立場がそうさせるのだろうか。 接していて何の違和感もないひとが、自分の得意な分野の話になると、とたんに上目線になる事も経験する。 自信の裏付けが態度に現れるのかもしれないし、本人に悪気はない筈だ。ただ、その場合でも物には限度というものがあり、居丈高に高飛車に話の腰を折ることは相手に不快な感じを与える。 一方、得手な話題でも黙って相手の話をニコニコと聞いてくれ、爽やかにその話題から離れるとしたら、かえってその人は随分と人が悪いことになる。誠に人とのお付き合いは難しいものだ。 かたや、上目遣いに見られるという言葉は、相手の服従姿勢のことを言うらしく、上目は上目でも相当異なった状況を指す。日本語は難しい。 上目線は見下ろすような様を言い、上目遣いは目だけが上を向くような状況ということだ。目は口ほどに物を言い! |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章の変化 ~ 「日記」考 ~ 平成24年4月2日 過ぎ去った日々を思い出すと、その時に感じた感慨とは異なった今の感じ方があるように思えてならない。確かな違いかどうかはわからないが、過去に書いたものを読み返すと、自分で書いたものであっても何か違和感を覚えることがある。どちらの思いが正しいのかは分からないが、確かに自分自身の書いたものであるので、自分の感じ方が変化してきているのかもしれない。 子供のころ書いた作文は、先生にお題をいただき、自分の思いのままを綴られたもので、愛らしく可愛く、時に大胆な文章であった。その後、大人になって、ロートルになり、様々な文章を書く機会を経てきている。多くは学術論文であり、依頼原稿であり、自身のホームページ・ブログ等だ。これらのすべては読者を意識した、第三者宛ての文章形態となっている。それでいいわけだが、例えば日記の場合はどうだろう。 日記とは本来、日々感じたこと、出来事を書き綴るものだが、時として誰かに見られることを想定した文章になる。しかし、その時点ですでに日記とはいえなくなる。日記は自分で書き、自分で振り返って読み、やがて廃棄するものだと私は思っている。だから本来体裁やらうまい下手は気にする必要が全く無いものだ。世の中には、日記と称した記録文が多く公表されているが、廃棄する予定がたまたま不幸な転帰の結果、作者にとっては不本意ながら家族によって公開される日記もある。しかし、それらの中にはどうも第三者を意識しながら書かれた、すなわち将来密かに読まれることを前提とした日記もある。私の考えでは、このようなものは日記とはいわない。 その時に起こった事象を正直に、誰に見せるためではなく記録をしておく習慣を多くの人々が実践していけば、そのことが恐らく社会をさらに深く洞察するきっかけとなるだろう。人に見せるかもしれないと思うから、文章は修飾され、自分の意とは多少異なることでも平気で書いてしまっているのかもしれない。かくいう私は日記を付けていないが、過去の発表文だけでも、はじめに書いたような変化がみられる。 捨てる予定で感じたことを書き留めておくと、世の中の変化がよくわかる。是非とも徒然なるままに日記を付けたいものだ。「もしもの時には、必ず見ないで捨てろ!」といっておいても、守ってくれそうにない家族がいるから辞めておこうか!? |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
団塊世代の一人として 平成24年3月15日 私は、いわゆる団塊世代の始まり昭和22年に生まれた。 世代人口最大の人数をほこり、背伸びする世代ともいえ、世代の中で頭一つ出るのも大変であった。 戦後日本を牽引した親におんぶに抱っこの世代。 地元の公立小学校では、余りにも多い人数のため講堂に間仕切りをして二部授業が行われた。 入学した公立中学は一クラス55人ほどで、18学級1,000人余の大所帯。先生に可愛がられるどころか名前さえ覚えてもらえず、卒業旅行は関西汽船を借り切り四国に行ったが、長いバスの隊列の先頭にはパトカーの先導があった。 とにかく目立つ生徒になることなど物理的に無理であり、トコロテンのように卒業した。 前年度の生徒数と余りに違う人数に、周りの教育関係者は戸惑うばかりだったのだろう。「その他大勢扱い」が多く、常に被害妄想を持ち、満たされない抑圧的生活送ることがしみ込んでいた。同級生の数が多すぎ統制が不可能に近く、小中学校での同窓会クラス会は、まとめ役さえいなく、未だに一度も開催されていない。 逆に、全共闘世代として世に対する反骨意識は強いが、それでいて社会に出ると地位にしがみつく世代かもしれない。日本の中心的世代とはなれず、数の多さ故、福祉でも「金食い虫」とされる。 世のため人ため、何らかのお役に立ちたいという気概を持つ者も多いが、とにかく学生時代に経験した突出した存在になれないトラウマを持つ者も少なくない。 現在、多くは定年を迎え、第一線から退きつつある。団塊世代による社会構造が今後高齢者として大きな塊となり、子供達や社会にどうしようと悩ませているのだろう。 ネガティブ・イメージの強い団塊世代だが、ポジティブシンキング&積極行動も得意だ。恐らく今後、私たちの志と社会的使命感が数の多さを武器に大きな力を発揮するのではないかと私は考えている。 まず、団塊の世代の責務は、残された活力を使い果たすまで若い世代を育て上げることであり、自分達より高齢の方々へのサポートだ。すでに自分達の親の世話は、老々介護になろうとしている者も多い。だが、まだ前向きな気持ちは残っている。 自分達が介護される年齢になるまでは、人様のお世話にも身を砕くファイトを持とう。高度成長の果実を貪り喰い、社会的奉仕を怠ってきたかもしれない我々が立ち上がらなければならない。我々の世代は昭和22年~25年生まれの世代責任が問われていることに気付かねばならない。 まだまだ汗をかき社会を下支えする役割を果たせるようそろりと耐え忍び余生を送るのではなく、出来る範囲でのボランティア精神を発揮せねばならない。 昭和22年生まれ、約265万人出生。現在の死亡者数80万人と聞く。 さて、これからどうする団塊世代の諸君! |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
四季の移ろい 平成24年3月1日 季節の変化は、なだらかに緩慢にじわじわと変わるものではない。 気温は、ある時ドンと変化し、急に寒くなったり暑くなったりする。 めりはりがあるのが、日本の四季だ。 1度、2度では体感温度変化を感じにくいが、5度違うと感じる。 年間を通じて30度以上の温度差がある。 微細な温度変化だと体が慣れてしまいやすく、温度中枢も麻痺し、体の変調が出やすいのだろうか。 そういう意味において、急激な温度変化が重要なのかもしれない。 経済はじめ社会的現象も、穏やかに緩慢に不景気になったり、じわじわと戦争になったりはしない。 ただ、緩慢に変化する現象もあり、これは曲者だ。 徐々に悪くなると、それに慣れてしまい、中々そこから抜け出せない。 明日の日も平和だろうと誰しも願うが、それが叶うかどうかは誰も分からない。 ただ漠然と信じるように、思いこむようにしている。 春の訪れを待ち続け、春爛漫を満喫し、五月晴れの端午の節句を慶び、恵みの雨に田植え歌を歌い、かんかん照りの太陽、そして実り多き秋の収穫、やがて厳しい冬を迎える。 四季の移ろいを、このように表現するが、実はその間の嵐への不安はいつも持ち続け、天に祈る日本人の姿がある。 平穏無事とは何を指すのか、四季折々不穏災難を潜り抜ける強かで雅な日本人であり続けたい。 間もなく3・11を迎える今、春を待ち続ける気持ちは、いつもとは異なる。 被災地の苦悶を少しでも分かち合い、芽吹く未来の到来を皆で願おう! |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
地震を体験した者として思うこと 平成24年2月15日 阪神淡路は、午前5時47分に発生。 東日本大震災は、午後2時46分に発生した。 人々はどうしても、その時間帯を主に今後の対策を考えがちとなる。 様々な災害発生状況で、シュミレーションは変化する筈である。 災害発生は、①早朝寝込みのころ ②朝食時or登校出勤時 ③午前中 ④昼休み時 ⑤午後活動時 ⑥下校時 ⑦5時以降 ⑧夕食時 ⑨就寝前 ⑩就寝後 ・・・さらに、1.春夏秋冬 2.晴雨雪風台風 これらの諸条件によって行動シュミレーションを想定すべきだろう。 加えて、Ⅰ地形 Ⅱ建築様式 Ⅲ乗り物の種類 Ⅳ道路の状況 Ⅴ組織&家族の危機管理状況が色々と状況を変える。 これら全てが噛み合いながら複合的に被害は拡大する。 だから被害の程度も様々となる。 発生から3日間は助けが来ないという想定での各自準備が必要のように思われる。 直下型地震だった阪神淡路では、縦にドンと来て大きく激しい揺れでミキサー状態となった。断層が走った狭い範囲で大きな被害が出た。道路一本挟むと何らの被害も生じていない所が多かった。 散歩中の人は地に腹ばい、道路が蛇のようにうねりながら迫ってくる恐怖を語っておられた。ロケットが飛び込んできた・嫁さんが突然殴りかかってきたとか、様々なその時感じたことを友人から聞いた。そんな馬鹿な、と思うようなことを瞬間感じる、脳の判断には時間差があるので、にわかに何が起こったのか分からないというのが実情なのだ。 東日本大震災のようなプレート型地震では周期の関係からか大きな振幅の長くゆっくりとした揺れだったらしい。マグニチュード9.0という巨大地震にもかかわらず建物の損壊はそれほどでもなく、後の津波により町々は甚大な被害を被った。 日本列島は四方海に囲まれている。大陸ではないということは、著しい地殻変動によって現在があることになる。平野部が少なく、山々を背骨とし、日本海溝はさらに深い。極めて劣悪な地形の中で日本人は住んでいる。 これからも長きにわたり日本列島は徐々に形を変えて行くのだろう。それに伴い大きな地殻変動が天変地異が日本人を苦しめる。 八百万の神は、今でも日本人の心の中に生き続けている。 それほど多くの神を必要としている日本という国に生きる我々。 千年後、万年後日本はどうなっているのだろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
情報というもの 平成24年2月1日 「今日な、歯がめちゃ痛うなってな、歯医者行ってきたんよ。そしたら、どっこも悪くありません、体調から来てるんですって言われたんよ。すっきりした感じやヮ~」「全然虫歯ないん、すごいやん!」「色々詰め物とかはしてるけどな・・・」「それ、分らんで!?歯は詰め物外さな分らんらしいよ!」「ほんま・・!・・・どないしょ~・・・!?」 二つ目に「詰め物を外さないと正確には診断が難しい場合があること」という指摘だ。これは実に的を射た話であり、視診・触診・レントゲン審査でも詰め物の中は分からない事が多いからだ。さりとて除去するには根拠を明確にせねばならないが、得てして同意が得られない場合が多い。結局、様子を見るケースが多くなる。 この方々ように優れた情報を持っておらる方が多ければ、町の歯医者さんも大変助かるだろう。 生きた情報というのが問われているが、中々そういう優れた情報というのは稀有なものだ。よく情報は勝手に転がり込むことはない、自ら取りに行く事が重要だ、と言われる。しかしながら、自ら取りに行く情報には限りがある。ネットはじめ情報は溢れているが、電車内での市井の方々の会話には生の声、優れた情報が溢れている。適度に混んだ電車が良いようだが、そういう目的で電車ばかり乗っている訳にはいかない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
いつものように 平成24年1月16日 日々是新しく光に向け歩み続け候、・・・。漠然とした明日への光がさしていた若いころと違い、歳相応の新年を迎えた。それでもお正月は何か新鮮な気持ちにさせてくれる。 壮年の頃、とある大先輩が「其の歳になってみないと分からないことがあるのですよ・・・!?」と何かの折に呟かれた。記憶に残っているこの呟きは、恐らく当時の私の勢いに忠告を発せられた為に、しゅんとした感慨として覚えているのだろう。 「いつものように」明日を歩むということが如何に難しく、如何に愚かしい事かに気付かされる。若いころは猪突猛進、少々寝なくともどうってことはなかったが、最近では同じリズムを刻まないと、たちまち体に変調を来すようになってきた。 つまりは、規則正しい毎日を過ごすのが自分にとって都合が良くなってきたのだ。裏返すと、若いころは無茶なリズムでも良いということになる。 規則正しい生活の大切さは小学校頃から教え込まれたが、世間の若者が言うことを聞くわけがない。若者の無茶は度を過ごさない限り、それで良いし、分別をわきまえるようになった大人は、自分自身が規則正しい生活をしなければ体がしんどい事を自覚するようになっているので、小さな子供にもそれが大事だと諭すのだろう。 「いつものように」という事は強い願望であって、明日の日は恐らく昨日とは違う自分がいる。さらに、周囲の状況も刻々と変化しており、どんな厄災が待ち受けているかもわからない。あるいは、降ってわいたような幸運に出会うかもしれない。たぶん、そういう連続で人生が織りなし、意味不明の事象が世界を覆い続けて行くのだろう。 明日への希望を持ち、大きく羽ばたく夢を追う。日本国中がそう望む新年を迎えた。少しの勇気と行動が豊かな日本に変えると信じ、「いつものように」さえ難しい現実を超えて、夢を追い続ける1年とせねばならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
生涯元気な歯の力 平成24年1月6日 平均寿命は2010年度で、男79.64歳・女86.39歳と伸び続けている。現在生まれた子供の平均寿命を指しているので、我々の場合は平均余命が正しい。 平均余命では平成21年の推計では、男65歳の場合18.88歳であり、平均寿命79.64歳と比し3年余長い。期待値推計なので、各年齢層により平均余命は異なり、平均寿命もまた違う。いずれにしても、長寿であることにはまぎれも無い事実の日本である。 若い頃は平均寿命が50歳だろうが、80歳だろうが、さして興味はなかった。この歳になると、前向きだけではなく、後のことを考えることがある。例えば80歳とすると、80歳以下半分はすでに亡くなっている。80歳以上半分が存命中ということになる。平均とはそういうことだろう。 さて、これほど高齢社会になった日本は、世界でも最も未知な世界に突入しており、世界が注目している。中でも社会福祉の面で、様々政府は苦慮しているようだ。年金問題は深刻で、高齢者比率がピークアウトするであろう25年ほど先まで、国民一体となり高齢者を支えていかねばならない。自立している高齢者も多いが、高齢者には病気がつきものであり、必ずいつか働けなくなる。個体差の幅が広く、年齢だけでは線引き出来ない、一概に生活状況を年齢により推測することも難しい。誰しも思うことは元気溌剌な年寄りでありたいし、寿命が尽きるまで元気でいたいと望む。このあたりが最も衆目の一致するところであろう。 歯科医療の目下の眼目は、生涯自分の歯で食事が可能となるよう、歯の寿命と人の寿命の差を縮めることである。仮に健康な歯が喪失した時には、人工臓器である義歯等の歯科医療で機能回復が可能だ。義歯も含めて「生涯元気な歯の力」が高齢者の生きる力の源であり、私の残された歯科医師人生の力を振り絞り挑戦すべき最重要課題だ。 参考1: 歯と健康寿命 ① 参考2: 歯と健康寿命 ② |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
一人ということ 平成23年12月15日 所用で上京し、家内は親父さんの米寿祝いで実家に帰り、犬達もお預かり。 東京では早朝大きな揺れで目覚め(震度3だったが13階だったのでかなりの揺れで飛び起きた)、予定を変更し早々に新幹線に飛び乗る。本当はお祝いに駆けつけるべきなのだが、用事があるので行けないことにしていた。 あまり良い婿ではない、というより米寿祝いとは特別のお祝いであるべきなのに本当にけしからん婿だ。 次第に、しんみりしてきた。 自由に一人で居ると、何だかいつものリズムと違い結構手持無沙汰となる。テレビも大して面白いものもなく、いよいよ孤独になってきた。 お茶を入れるのも面倒くさく冷蔵庫のペットボトルの水を飲む。 やらなければならないことは山ほどあるが、順序立てて前に進める気にならない。 子規は「病床六尺」という新聞連載を書いた。 偉大なる近代俳人の死期のせまる空間での執筆だが、確かに起きて半畳・寝て一畳とは良く言ったもので、さして広くも無い拙宅だが、一人で居ると広すぎる。やたら広すぎて不便だ。ガラクタは捨ててワンルームがきっと良いぞ、とか取りとめなきことばかり考えていた。 夜となり、テレビを見ながら酒を飲み、それでも一応パソコンで気付いた事をメモし、また酒を飲み早々に就寝。 爽やかな朝を迎え、新聞でも・・・と思っても自分で取りに行くのだと、はたと気付き狼狽。 仕方なく自分でコーヒーを入れ、昨日買った期限切れのサンドイッチを頬張り新聞に目を通す。もうすることは無い。昼はカップラーメン、夜はレトルトカレー・・・。 そうして、一日半の一人生活は終わった。 実際には洗濯もし、買い物にも行かないといけないし、銀行にも行かねばならないだろう。 考えただけで生きて行く大変さがヒシヒシと感じられる。 もうこれはすさまじい重労働が日々の生活にはのしかかっていることになる。 生きて行くには甚だ過酷な家事をこなさねばならない事を知った。 世の中には不幸にして連れ添いに先立たれ不自由な生活を余儀なくされている同輩がおられることだろう。つくづく家内の存在に感謝する一人生活だった。 纏わりし 愛犬いなく 凍え部屋 一歩 私の母は父が死んでから、28年間嬉々とした生活を送り、勝手気まま自由奔放な余生?を送った。 --------------------------------------------------- 「日々感じること」の年内の更新につきましては今回を最終とさせて頂き、年明け最初の更新は1月6日の予定にしております。 それでは、みなさんいい新年をお迎えください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
犬談議 平成23年12月1日 テレビ「南極大陸」を楽しみに見ている。幼い頃が懐かしく思い出される。ドラマでは犬ぞりが大活躍している。 犬達のリーダー「リキ」を見ていると我が家の「葵 アオイ」とよく似ている。ウルフシェパードで精悍な子だ。今はほとんど警察犬訓練所に預けっぱなしなので、めったに我が家には帰ってこない。葵とリキがたぶり、「南極大陸」のリキは殉死してしまう、可哀そうだ・・・。 ハスキーや樺太犬やエスキモー犬は力強く突っ走る大きな体が特徴で、下毛が発達し、零下数十度でも対応可能、たくましい犬! 元々犬は、オオカミやキンイロジャッカル・コヨーテを祖先にしたイヌ科の動物。ヒトに飼われるようになり改良が加えられた。特に西洋犬の多くは耳が垂れている。あれも改良されたもの。オオカミやシェパードは耳が立っている。子犬の頃は垂れ耳だが、次第にピンと立ってくる。ドーベルマンは品種としては垂れ耳だが、耳を切りテープで無理やり立った状態で固定する。動物保護の観点から最近では切らない傾向もある。和犬の耳は全て立っている。何千年も改良されてないためだ。土佐犬は垂れているが、あれは秋田犬とマチシフのミックスらしい。和犬は飼い主に忠実で、家人以外にはなつかない性質が濃いい。猟犬としての和犬はだいたい単独行動だが、洋犬は狩りの用途で犬種を使い分けする。 キツネ狩りではビーグル犬を多数放ち、狐をビーグルの鳴き声で追い込む。別名森のシンギングドッグとも言われるほど鳴き声がよく通るが、逆に家庭犬としては、やかまし過ぎかも・・・!? トライカラーが可愛いのでディズニーの世界にも再々登場する。ダックスフンドなどは、アナグマを追い詰める目的で胴長になっている。穴の中に鼻先から入っていく性質が備わっている。 リトリーバ―犬には何種類かいるが、いずれも撃ち落とした鴨や鳥を拾って持ちかえる性質を利用して人間が行けないような川や沼に入って行く。ポインターは文字通り、狙った獲物の周囲に行き、片足を上げてポイントするような性質を活用している。(これら犬の話題は記憶に基づいたもので、誤りがあるかもしれない。) 犬は何千年も来居を共にしてきた忠実な人間の仲間。飼い主のマナーを始め、都会での飼い方には厳しいルール遵守が求められる。そのうえで、最愛の家族として共に人生を歩む喜びを皆で共有したいものだ。犬の生涯は短い。生まれてから彼の岸に向かうまでの生涯を見とれるのは飼い主だけだ。 片や人間の生涯は、親から子へ引き継がれ、その生涯を見続けてくれる者は神仏だけだ。そういう点でも犬から学ぶことは極めて大きい。 飼い主は犬にとって、神のように生涯を見届けてくれる存在なのだろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
記憶の曖昧さと現実という矛盾 平成23年11月15日 雑誌を捨てようとし、何気なくパラパラとめくっていると「東京電力」という織り込み広告が目に付いた。昨年の文藝春秋12月号だ。見開きのインタビュー形式の広告だが、それまでも繰り返し広告記事が掲載されていても内容を読んだことはなかった。 前社長とインタビュアーの記事を読んでみて、3・11震災後から今も続く悪夢のような出来事を予見させる内容は全く感じられない。未来に向けて、圧倒的楽観的希望的な広告記事。繰り返し読んでも、何やら虚しく、昨年12月東京電力の快進撃記事は現実と乖離しすぎた悲しいものだ。 ビスマルクは「愚者は経験に学び賢者は歴史に学ぶ」と言った。私達は常に歴史検証から未来に向けた希望を模索しようとする。しかし現実には時系列に現象を並べる際に、今の時点で時間の流れを考えるだろうか。過去を振り返り、失敗を繰り返さないように努めるという経験則に則った動きはするだろうが、客観的歴史検証に基づいた動きをするのは不得手に思える。 私は愚者なので、人生を振り返ると、その時その時の判断で、へまな事ばかり繰り返している。歴史に学ぶという概念は理解していても、現実は瞬間瞬間を必死に生きるという現実がある。余裕を持って日々を送った記憶はない。神戸に大地震が来るとの概念も皆無だったし、起きた時も何が起こったのか瞬時には判然としなかった。それほど連続的に人は賢く生きるとは考えにくい。 東京電力の広告記事もその時点で誰も疑問には思わなかっただろう。電化製品や食べ物の広告と違い、電力会社の広告の主眼が理解しづらいので、たぶん誰もこの種広告記事は読んでいない可能性がある。読んだとしても、何ら印象には残らず、まして批判めいた感情さえ抱かなかったのだろう。 様々な批判が現在東電に対して渦巻いている。もっともな内容ばかりだが、事故前の感性に呼び戻された広告記事に、自分達は一体今まで何をしていたのかと暗雲たる気持ちとなる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
歯科医療の空洞化 平成23年11月1日 空洞化は、構成していたものが消滅、移転等することによってそこが空き「空洞」になる状態と言われているが、ことに現在の日本における産業の空洞化が問題視されており、海外に工場移転する企業が多くなると懸念されている。 歯科医療においては、今言われている空洞化は当てはまる問題は見られない。ただ、将来も含めた歯科医療の中身が問われていることも考えておかねばならない。
時期に応じた様々な困難な課題克服が求められ、そういった困難な課題は否応なしに訪れる。 その都度、問題提起を行い、可能な限り国民歯科医療の困難を克服し、さらなる高見を目指す歯科医師であり続けたい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
右と左 平成23年10月15日 眼で見る相手は、左側があいての右・右側が左手となる。 自分を鏡で見た時には、右は右・左は左に見える。だから人が自分を見る時とは逆転している。人から見ての自分は、自分では見てないことになる。写真を撮ってもらうと、人が自分を見ているように写るので、その写真を見ると、鏡の中の自分とはどこか違うように見える。鏡は物体の左右を逆転させるが上下は逆転しない。 朝永振一郎「鏡の中の世界」が学生時代に試験に出たことを覚えている。物理学での鏡の世界は難しい。科学と哲学を混ぜたようで私などには理解しづらい。 さて、医療の世界ではレントゲンにしてもカルテのスケッチでも何でも左右逆転で表示することになっている。それは見たままを記録するためであり、患者さんに対する時、術者は左右を逆だと常に意識しながら診察し、施術する。当たり前のことだが、これを訓練し続けないと取り返しのつかない間違いが起こる可能性もある。 向かって右は患者さんの左なのだから、病変をカルテに左と記載した場合には、患者さんと対面した場合、向かって右を探さねばならない。右と記載されていて左を検索すると大間違い。このような間違いは万が一にも起こらないように注意意深く診療が進められている。 ところが、患者さんと対面せず、後ろ側から口を覗くと左右が一致する。歯科治療では斜め前方から治療することが多いが、時には頭の後ろから口中を治療することもある。患者さんの右前方から拝見しながら、治療中に後頭部に術者が回りこむとき、いつの間にか鏡の世界に入り込んでいる事がある。この現象には常に気配りしながら診療をしている。 患者さんにレントゲンを説明する時、ご自身のレントゲンで右左が逆転していることを説明させていただくが、実際にはご本人は頭がこんがらがっておられるかもしれない。これらは日常生活でも起こりえる事で、例えば国会の右翼左翼は議長席から見てなのか、傍聴席から見てなのか? 野球で右翼左翼はホームベースから見てのことだが、外野席で観覧した時、イヤホンで野球中継を聞きながらの場合、左右は逆転する。でも、そんな当たり前のことは自然に体で理解しているものだろう。 医療の初歩中の初歩のお話だが、基本を忠実に押さえながら、全国の医療は安全に遂行されている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
整理整頓 平成23年10月1日 今回、16年間活躍した冷蔵庫を買い替えた。冷蔵庫は台所の一番奥にあるので、まず食器棚を移動しなければならない。 大きな水屋には不要な食器類が押し込められていたので、結局水屋を捨てることになり食器類も整理するはめになった。震災で助かった台所流し台の下を見ると、奥には、子供の頃に使った懐かしい食器もあった。 小学校給食時のアルマイトボール様食器、いつの頃のものか古びた梅酒容器(梅と梅酒が少々入っていたが口にするのははばかられた)。どれもこれも何の価値も無いものだが懐かしいものばかりである。親子で懐かしいもの・夫婦で懐かしいもの・両親を思い出すもの、しばし感慨にふけるが、どんなに思いが込められた食器類だろうと、ハッと我に返る。とにかく捨てなければならない。3代、4代後には思い出どころか我々が先祖となった時に品格さえ問われかねない。 ガチャガチャと食器棚の不要な食器類を捨てるのも大変。使うかもしれないと思うものは段ボールへ。すると、それを納める納戸を整理するはめとなる。一か所整理しようとすると次から次へと整理の悪循環が始まる。いつ終わるとも知れない長い時間と疲れを夫婦で味わうこととなる。 思い出というものも、やがて風化し、仏壇に思いをはせても魂に祈るのみで、遥か昔の先祖の顔さえ分からない。とにかくガラクタは捨てなければならない。何が何でも捨てると決めて家の掃除・整理整頓をしようと決めている。 しかし、あまりにも多いガラクタにため息しか出てこない。あまつさえ最近ではゴミを捨てるのにもお金がかかる。 粗大ごみが自分とならないように努めている今日この頃。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
災害列島日本 平成23年9月15日 台風12号は大水害という厄災を紀伊半島中心に撒き散らし日本列島を去った。とんでもない雨台風だった。速度が遅く、その分雨量は途方もない量となり、三日三晩降り続き、保水量を遥かに超え、山では土石流となり駆け下った。人々は声をそろえて「経験の無い・生まれて初めて・・・」という感想を述べている。 東日本大震災でも、「未曾有のかつて経験のない」という表現が頻繁に使われた。吉村 昭氏の「三陸海岸大津波」を読むと、過去何度か同地区は津波に襲われていることが分かる。古文書による過去の記録からも津波被害が窺い知れると記載されている。少ない情報量だろうが、古い言い伝えや古文書から、正確性には幅があるものの、ある程度過去の災害が浮かび上がる。 私が住む神戸も再々大水害に襲われている。昭和13年の神戸大水害では土砂災害により600名以上の方が亡くなっておられる。子供のころ、流れ下った大きな石が集められていた所で遊んでいた記憶がある。その後、昭和34年、昭和42年にも洪水被害が起きた。昭和13年の大水害の際には現在のそごう百貨店前が川になったそうだ。生田川は元々の川筋を東側に変えたらしく、洪水の際には源流通りの場所であるそごう百貨店前あたりを冠水させたようだ。 昭和34年の洪水の時、私は12歳だったので、当時の事を覚えている。六甲山系からは幾筋もの川が神戸市内に流れている。神戸市東部では住吉川が最も大きな川だが、それでも川幅はせいぜい20mぐらい。標高931mの六甲山からおおよそ8kmで大阪湾に流れ出る。二級河川で普段の水量は決して多くはない。私の住む田中町を流れる川は「天井川」という。由来は河底が堆積層により周辺より高い位置にあるということらしい。その洪水の時、水は住吉川と天井川の丁度中間点の十二間道路を川にした。天井川の東隣に位置する我が家は河と同じ高さなので、さらに東部の南北の道筋が川となった。芦屋川が天井川の東に位置するので、その中間点が川となったように記憶している。 このように、その土地その土地には伝承していかねばならない災害の経験がある。私達の人生の長さでは経験しない天災が、その土地で過去に起きているものがあるかもしれない。 穏やかな地と言われる神戸も、何度となく大災害に見舞われている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
もたれ合い 平成23年9月1日 もたれ合いという言葉は辞書検索では見られない。「もたれる」で、「寄りかかる・甘えて頼る」という解釈がある。 今回の原発報道では「もたれ合い」という言葉を、繰り返し見聞きしたように思う。互いの利権に沿った「寄りかかり」という意で報道されている言葉のようだ。あるいは新語なのだろうか? 類語として「腐れ縁」という表現もされている。どうやら、「もたれ合い」とは悪いイメージの慣れ合い的な事を表す言葉のようだ。 「甘えて頼り合う」と解釈すると、良い意味でも使えるような気がする。例えば、家族の中で、特に親子関係にあっては、幼い子供たちと親の間には甘えるという「もたれ合い」がある。他人とでは決して許されないことでも親子の間では認められることも多いし、その「もたれ合い」こそが親子愛なのだろう。時として恋人同士には錯覚と誤解による「もたれ合い」もあるだろう。「あばたもえくぼ」となる愛情があってこそ、人類はここまで生き延びてきた。騙し合いでも良いから恋人同士の愛が共に白髪となるまで続いてくれれば万々歳! 社会生活にあっても、「もたれ合い」という事はある程度容認されている。ただ一つ「厳しい中でのもたれ合い」という点が家族での場合とは随分異なる。相互扶助という社会生活の基本からすると、厳しいということは法律という規範で最低限度の監視が行われていなければならない。規範を逸脱すれば法で罰せられるが、ここで言う「もたれ合い」構造が一般的認識を超える極めて「ぬるいor緩い」利権の相互扶助や、互いに保証人となるようないかさまが横行するとなると、極めて問題のある「もたれ合い」となる。 国同士の「もたれ合い」もある。安全保障、不可侵条約など様々なものがあるが、過去に国同士の約束を反故にされた悲劇もあった。互いに信用・信頼することが基本だが、裏切られないという保証はない。 願わくば、皆がもたれ合える美しい日本であり続けて欲しいが、もたれ合うための信頼関係と規範を守る心の熟成も大きな課題だろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
涙、色々 平成23年8月16日 感情の動物人間は、涙を流すことがある。その頻度は人それぞれで、私のような涙もろい者は性格的弱さを露呈する涙が多い。悲しい時、寂しい時、感動のあまり、という涙。怒りの涙は経験がない。うれし涙というものもある。 感情の起伏には人により幅が大きいので、涙に繋がる事象も一定ではない。ちょっとした事でも泣く人もおれば、涙をこらえて泣かない人もいる。 赤ん坊は泣くのが仕事のようなもので、意思の疎通手段として泣く行為で母に乳を求める。年を取ると涙腺が緩むとも言われ、赤ちゃん返り現象かもしれない。人が見ていて感動が伝わってくる涙がある。高校球児の無念の涙は、こちらに十分伝わってくる。もしヘラヘラ笑っていたら感動を覚える場面は非常に少なくなる。 私は、感極まるとすぐに落涙する泣き虫中尾という異名も持つ。自分よがりな所が他人には不愉快に写る場合もある。「何を泣いてるねん!?」と思われる場合は、たいていが自分勝手な自己陶酔世界の中での涙の場合が多い。 涙もろい私にはこんな思い出がある。娘の結婚式での、娘からの手紙というやつである。あの場面、多くの両親は感動の涙にむせぶことが多い。私は、どうすれば泣かずに済むかを考えた。結婚式前夜、娘にどういう手紙の内容か見ておきたいと半強制的に手紙を見た。確かに泣けてくる。これはいかん!何とかせねば・・・!? 妙案を思い付き当日を迎えた。私を知る会場の来賓の方々こぞって、今か、もう泣く!それ行け!と私の涙を待ったが、一滴の涙も無くセレモニーは滞りなく進行した。娘が親への感謝を綴った手紙を読んでいる間中、直立の私は必死で自分の足をつねっていた。思いっきりつねり、その痛さに堪えている間に娘の語りかけが終わり、会場は拍手に包まれた。世の中には馬鹿な父親もいたものだ!? |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
これからの日本!? 平成23年8月1日 時は元禄 大江戸八百屋町・・・265年間続いた江戸時代は、極めて安定的で戦争動乱もなく武家社会であっても武力行使を行うこともなく、治安維持も良かった。 徳川幕府による全国諸藩の統制も上手く行き、大飢饉や大災害もあったが、全体には民衆安定期だった。士農工商という身分制度はあったが寺子屋はじめ教育も充実し、人々の考える力が付いた時代だったのだろう。鎖国という閉鎖状態の維持で世界から孤立していた弊害もあるが、それによる日本独自文化の醸成も可能であった。 幕末動乱から明治維新に入り、混乱の中、帝国主義的世界に向き合うこととなった。その後様々な変遷を経て今日を迎える。つまり黒船来襲までの江戸時代は大変安定した時代であり、経済的な成長は鈍かったものの、人々の生活は質素倹約を旨とした成熟社会であったと思われる。 さて、太平洋戦争後、日本は復興から高度成長期を迎え、世界第二位の経済大国となった。しかし、バブル崩壊後、失われた20年と言われる経済的混迷が続いている。今般の東日本大震災を被り、日本は最早黄昏国家とみなされる向きもある。 確かに様々な社会現象で経済停滞からくる雇用の問題や国の負債残高への対応、さらに原発問題・・・、山積する課題に悲鳴が聞こえる。でも非観してばかりしていても課題解決にはならない。 恐らく、今後長きに渡り日本は成熟型社会として世界的にも極めて希有な国であり続ける可能性があるように思う。高度経済成長は無い、大きく沈むことも無い、という状況を維持して行くのではないか。社会保障充実と高学歴、高い技術による高付加価値型技術立国、低成長と倹約、・・・、それらによる比較的安定的社会の維持が続く。 思想信条も大きくぶれず、宗教的なもの、あるいは日本文化も安定的推移を経る可能性が強い。ある意味では社会主義的な国のようでもあるが、日本独特の職業格差のない、富の再分配が行われる国。大きな歪もなく、大儲けする要素も少なく、低生産でも安定した生活を求める国。 そういう日本が長く続いて欲しいと、勝手に思っている。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
古老の話し 平成23年7月19日 今日は暇だったので、患者さんの話をゆっくり聞けました。 御年92歳の紳士曰く、「この辺りは『武庫郡』と言っていて、田んぼばっかりだった。本山駅は寂しい駅で、人がほとんどいなかった。昭和はじめの神戸大水害では大きな岩がゴロゴロ流れてきて、家々は濁流に浸かり、後始末が大変だった。道をふさいだ岩を、工兵隊が爆破して取り除いた。空襲も、川西工廠を中心に相当やられた。阪神淡路も大変だったが、後は火を出さないように人生の締めを考えている。」 時の流れに逆らわず、あるがままに生きるちゅうことでしょうか。 昔が懐かしいという懐古主義ではないが、電燈一つで暮らしていた幼少時を思い出すと、別にどうということは無いように思う。 歯科診療台も立位だったし、電気エンジンの前は足こぎエンジンだった。 冷蔵庫・洗濯機・掃除機・エアコンがないなど全てが電気の現代では考えられないが、別にそれで普通と皆思っていた。 真夏はあまり仕事していなかったように思う。 でれっとして、何とか過ごしていた。 とにかく、今ほど家が密集してなかったので、打ち水だけでも風が入ってきていたのだろう。 それと国道以外は舗装されてなかったので、今とは違うコンクリートの塊の街ではなかったように思う。 まあ、何とかなりますよ! |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
COMPACT ・ SLIM ・ 豊か・文化的日本の未来 平成23年7月5日 今盛んに言われているこれからの日本の未来は、おおむね表題のような言葉に集約されるように思う。 それぞれを辞書検索すると、どうやら日本的言葉と外国における言葉に二分されるようだ。 COMPACTとSLIMは適切な和訳が見当たらない。豊かと文化的は、英語では色んな表現があり日本語での表現と必ずしも一致しないように感じられる。 COMPACTの和訳は「小型で中身が充実していること」となっている。 これでは、少し意味が薄れてしまう。 今言われているCOMPACTとは、日本が重厚巨大産業を主体とした輸出依存型国家から知的産業国家に生まれ変わることであり、労働集約型産業からの脱皮を示しているのではないだろうか。 農業漁業畜産を軸として、メーカーのあり方も変わり、サービス業を主体とした知的労働へのシフトを目指そうとしているのだろう。 SLIMとは「ほっそりとしたさま、細身できゃしゃなさま」となっている。 この言葉も目指す日本の未来の姿とは少々異なる。 少子高齢化の時代に沿って、身の丈に合った適切なダウンサイジングが望ましいということだろう。 豊かという英訳は様々なものがあり、例えばRICHが検出される。少し違うだろう。精神的豊かさが尊ばれる時代となったというのが日本的解釈。 文化的とはCultural なのだが、日本人が言う文化的とは何かニュアンスが違うように思う。恐らく文化的とは創造性豊かな娯楽、芸術、趣味、生け花、スポーツ全てを表したもの。生活臭のする幅広い多様性ある人々の生きざまを示すものだろう。 理想論過ぎる論調かもしれないが、総じて感受性豊かで創造性逞しく秩序を重んじる日本人の特性が滲み出る社会を待ち望んでいる国民が多いのも事実だ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
エネルギー問題 平成23年6月1日 私のような歯科医師が悩み考える問題ではないかもしれないが、一国民として・電力を日常的に使わねば仕事にならない者として考えてみたい。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
歯科医師の技量 平成23年5月31日 「学識に富んだ歯科医師の技量」と「親身に患者の立場で考えてくれる歯科医師の優しさ」、そして「出来るだけ安価な窓口負担」が求められる世相、当然だろう。 脂の乗り切った壮年歯科医師時代と現在の老年歯科医師の自分とでは、何が変わったのだろう!? 一言で評価すると、今は積極的ではないかもしれない歯科医療の内容。 だからと言って壮年期の自分が良かったのか、今が良いのかは分からない。 全てに慎重であり、自然な帰結を望む診療姿勢となったのであり、消極的という言葉だけでは片づけられない一面がある。 とあるご老人も診療の際に言っておられた。 「前立腺の数値が少し高いので検査しましょう」と言われ、同意して生検してもらったが「苦しくて苦しくて、麻酔して針刺して・・・。大丈夫だったのですが、ね~・・・!?」 う~ん、このあたりが少し若いお医者さんと老練のお医者では違うのかもしれない。 83歳である数値が少し上限を超えていても、様子見をするのが老練な医師なのだろう。拙速に相手の年齢も何も考えない医療はしない筈だ。 だからお金儲けとはほど遠くなるのが老練なお医者かもしれない。 一人のお医者の人生における診療姿勢は時間の流れと共に変化する。知識と技能を集積し、脂が乗り切った医療と言われる年代は、大凡40代後半かもしれない。 では50代、60代は下り坂で医療提供の質が落ちるのかというと、そういう訳でもない。 卒後10年ぐらいは危なっかしくて見てられないのか?そうでもない。まずもって情熱が半端ではないし、恐れ怖さ知らずの逞しさがある。 誰しもが認め、皆が診療を望むお医者よりも、相性が良く確かな技量と柔軟性、熱意をいつまでも持ち続けるお医者を世間は求めている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
阪神淡路大震災と明石海峡大橋 平成23年5月14日 平成7年(1995年)1月17日午前5時47分に阪神淡路大震災が発生した。 淡路島北部を震源とするM7.3の直下型大地震。 当時、明石海峡大橋が建設中であり、地盤が1mずれ、大橋も何十cmか伸びたとされている。 当時の風評で、大橋建設が地震の引き金になったのではないかと実しやかにささやかれたものである。 しかし、資料を調べてみると、淡路側の基礎であるアンカレイジ4Aは岩盤上に直接設置されており、震源地深さ16kmのトリガーとはなり得ないことが分かる。 写真は明石海峡大橋全景で、左手が淡路島で四角いコンクリートがアンカレイジ4A。 雄大、壮大な大橋だが、地球からすると産毛ほどのサイズでも無い。 世界最高峰エベレストでさえ、8.848m。 今回の東日本大震災では、500kmに渡る地盤が動いたとされている。 とてつもない巨大地震だ。 風評被害も含めて苦しみのさなかにある被災者の皆々様への応援は勿論、神戸の私達の心は被災者の方々と共に在り続ける。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ユッケ食中毒に思う 平成23年5月10日 大腸菌0111のベロ毒素により尊い4名の命が奪われた。 下水道整備・公衆衛生の向上・栄養バランスは戦後飛躍的に改善し、世界の中でも日本は極めて清潔な国になった。日本人の清潔思考には定評があり、事実あらゆる面で食の安全性が担保される国になった。 今回の食中毒で一つ気になることがある。それは、清潔な社会になるほど人々は安心感が高まり、次第に無防備になっているのではないか?その一例として、生食という食習慣は電気冷蔵庫普及まで、ほとんどなかった。私の記憶の中の幼少時、刺身すらなかったように思う。何でもかでも全て加熱調理された物を食べていた記憶がある。牛肉は貴重品の頃だから、そういうことは参考にはならないかもしれないが少なくとも生肉を食べるという習慣はなかった。 どうやら日本人の細菌への免疫力は確実に落ちていると思われる。開発途上国への旅行では生水はご法度ということが定着しているし、それはとりもなおさず、そういう環境には適応出来ない体になった日本人があるということだろう。 感染症を研究してきた者として、感染症への対応と予防策は確実に成果が上がっていると考えている。一方で、病原力の強くない微生物には、むしろ多少不潔な環境が免疫力を上げると思っている。適度な不潔さによる強かな体作りがあっても良い。所が、それを具体的に研究することは叶わないし、極めて難しい。 何故なら、不潔な環境にさらされた場合のリスクを考える時、今までの研究成果を否定しかねないし、国民の理解は到底得られるものではないからだ。清潔の徹底運動あるいは予防研究が今後の未来を明るくするものであるし、清潔向上をさらに高いレベルに設定する方が無難だ。 しかし尚、私は「適度な清潔」と言葉を言い換えて、今後の社会のたくましさにも大きな期待感を持ち続けている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
東日本大震災から2カ月 平成23年5月9日 5月10日で東北大震災から早くも二ヶ月。 神戸にいては、どこまで復旧して、復興へ向けて動いているのかわからない。 体育館などの避難所に2ヶ月。プライバシーもなく、食事もあてがいぶち、それも相変わらずおにぎりやカップ麺に戻ってきているとも聞く。 地元保健所が「体育館は本来運動をする所で、調理を行うことはまかりならん」とのお達しを行ったともいう。それこそ杓子定規、避難民に対する愛情や助け合いの心は見えない。 災害出動で八面六臂の活躍の自衛隊。食事は缶詰に携帯食。食事をしているところを一般人に見られてはダメ。仮設風呂を設営し、避難民にしばしの安らぎと、衛生面という人間的な環境を提供していても、当の自衛隊は入浴禁止。約24万名の自衛隊員の中から、10万人を現地に派遣しているということは、交代要員なし。現場で汗を流している人間に冷たすぎる対応としか思えない。 福島原発で作業している人間も、つい一週間前まで、十分休息するスペースもなく食事も粗食。金銭的には恵まれていても、あまりに差別的な待遇。 震災から二ヶ月、食事とプライバシーの守られた十分な休息は避難民にとっても不可欠。いまだに、おにぎりにラーメンにカレーでは、棄民されたとしか感じられない。 とかく、このような対応しか浮かばない政府では復興もままならない。 国が守るのは文化的で安全な生活の保障。「想定外」であっても自分の家族がその状態におかれていたら・・・!? 東北人は我慢強いと言われているが、もう限界ではないか。 被災地域は広域で分散しており、孤立した集落も多い。一例として、被災地に給食センターを作り、被災者を雇用し、給食、配送を行うだけでも、生活の質は大きく向上すると思うし、働くことにより生きる意欲もわいてくるのではないか。 「ひとにやさしい日本」が幻想で終わらないように。地に足がついた施策の早急な実行は無理なのだろうか。 衛生面でも、夏を迎える被災地が心配でならない。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
日本の将来を考えてみよう 平成23年4月28日 東日本大震災を受けて日本は変わろうとしている。変わらざるを得ない状況となった。厄災と諦め、成り行きに任せるということは日本人の性格からしてあり得ないだろう。どのように変わるべきか様々な意見が噴出している。 {復旧} 一番目には、被災地域の再建問題だ。議論百出状態だが、一般的には地元住民の意に沿った再建計画が優先されるべきと考えるが、都市計画など色々な防災対策を講じた上での再建、特に町ごと津波で流された所では多少時間がかかっても素晴らしい町に生まれ変わることが期待される。 二番目には、原発問題だが、原発廃炉までの道程は険しく、難題を一つ一つ乗り越え、相当な長期間を覚悟して臨むことだろう。その間の避難者への対応もかつてない行政の卓越した指導力が問われることになる。最終処理までの長い年月、原発周囲数キロの土地については、行政管理区域とするのか、あるいは近い将来帰宅可能となるのか情報開示されなければならない。それらへの道筋にはまだまだ不透明な事が多い。加えて、今後の原子力政策の見直しも喫緊課題だ。 三番目には、現在日本における経済不況からの脱却・財政再建への遠い道程の克服が、大きな問題として立ちはだかっている。これらについては市民運動でどうにかなる問題ではない。政府主導の力強い方向性が示される必要がある。 {復興} さて、日本の将来と言っても、50年ぐらい先までをまずは考えておく必要がある。100年以上先のことは責任ある発言にならないし、たぶんに情緒的観測となってしまう。50年先までを10年で区切ると5段階となる。震災復旧には10年は見ておいた方が良いかもしれない。その後10年で復興、新しい町に生まれ変わることだろう。さらに、その後10年刻みで日本再生計画を進め、50年後には全く新しい日本とならなければならない。 再生を目指すのではなく、新生日本でありたい。古き文化を継承しつつ、新しくコンパクトな新生日本。勇気、希望溢れる日本としなければ大災害被害者への鎮魂とはならない。国民の一体感創出で、恐らく近未来、日本は新しい国に生まれ変わり、世界的にも稀有なコンパクトで効率の良い国になるように思われる。今までの価値観が変化し、より自然を愛する震災立国になるのではないだろうか。その為にもグランドデザイン・ビジョンが重要となる。 {新生日本} 今現在日本が抱える課題には、先の経済問題以外にも世界的に未経験の分野もある。急激な人口減少・超高齢化・少子化のキーワードを織り込んだ将来予測が必要。50年後人口は約8,000万人程度とされ、現在より5,000万人弱の減少が見込まれる。同時に65歳以上の高齢者数は3,500万人程度・15歳以下が1,000万人程度ではないかと推測されている。 つまり、労働人口は国民の半数、4,000万人で、現在の半分。超成熟社会の到来であり、現在と同様の国民総生産の維持は到底不可能であり、物事の捉え方・考え方を根底から変化させなければならない。 {医療福祉} 20世紀を振り返ると、様々な事があったが、拡大し続ける社会であった。健康への期待感も強く、医療は断然世界一と言われ、充実した社会保障の一翼を担った。臨床研究も盛んであり、何より安定的収入・社会的信用等から医学部を始め医療系職種が人気を集めた。向こう50年では医療の内容を向上させるにも限界があり、恐らく臨床家養成の量的要望は強くとも、さらなる優秀な医学への求めは薄くなるだろう。つまりは、老齢化対策・少子化への対応要望が強くなり、臨床家養成も頭打ちになる。保健師・介護士ニーズが高まり、病院・診療所の在り方も大きく変化を来している筈である。 病院、診療所は充足し、医療へのインフラ、人材育成は頭打ちになっている可能性が強い。検証に基づいた推測でなければならないが、どうもこれらの点はあやふやだ。一番重要なことは、医療ニーズは減少するということ。際限なく医療費は右肩上がりだったが、これからは終末期医療の在り方と介護費用の増加問題。つまり、医科歯科とも個人開業医の収入は頭打ちから減少局面に入る時期が必ず来るということ。 命長らえるのには限界が来つつあるので、生活の質転換の時代に入るのが先。団塊の世界がほぼ居なくなる25年先、超高齢化率よりも、少子化による人口減少でバランス良い時代が30年ほどで迎える。 しかし、その後、20年で労働人口減少からくる社会的状況が今とは全く異なるものとなるように思う。つまり、現在幼少期にある者達の時代、あるいはその子の時代が50年先の日本ということである。 {社会進化} 現在言われている限界集落は崩壊集落となり、日本国内での都市部・郡部は整理整頓されるか、昭和22年頃の人口動態とほぼ同じなのだから、そういう村落形成とならざるを得ないだろう。 つまり、全てが収縮し、よりコンパクトで効率性のある都市となっているだろう。電力供給はじめ全国展開の維持管理が必要な社会インフラも、その在り方が問われ、大規模なものは少なくなり、小さくても効率的な町づくりが必要となる。 大規模の町を維持するのは相応しくなくなり、交通網も大動脈の維持管理が最低限の課題であり、列車の間引き運転等が当然のことになる。 つまり、現在と同じ感覚で大きな日本を維持管理出来ない状況となるので、人と物の移動も制約され、やはり村単位での生活が基本となるのではないか。 ただ、ネット社会はさらに先鋭化し、物流依存も宅配等の伸びが予測される。 {時代回帰と未来への模索} 昭和30年までは、戦後復旧時代であった。炭・練炭が家庭での燃料であり、電気は電燈にのみ使われていた。洗濯機・テレビの普及は昭和40年頃までの間で、その後は高度成長時代として今現在に繋がる。昭和30年までの戦後復旧時代を知る人にとって、その頃が不幸だったとは思わないだろうが、さりとて時計の針を戻すのは叶わないし、その必然性もない。ティシュペーパーも無く、いわゆるちり紙だった時代はリサイクルの時代でもあり、家庭で出るごみも燃やして熱源とし、包装紙などという、しゃれたものより新聞紙が多用されていた。極めて少ない熱量で過ごしていた。それが良いのではなく、進化した現代社会を一歩前進させ、さらに高率で熱効率のよい社会を目指す方向に向かうということだろう。 蓄電、太陽光をはじめとした自家発電が主流となる社会がもう間もなく誕生しようとしている新しい時代。家庭菜園も当然となり、畜産農業・畜養漁業により質的量的な変革がなされ、使い捨ての物と長く使うものの峻別、江戸時代の良い所と現在のグローバル社会をミックスした快適で意義深い空間が広がる未来はすぐそこにある。 {不確かな未来への希望} このような予測の元に考えなければならないのはお金のことである。どう考えても現在の流動資金を維持管理することは不可能であり、一度大胆にリセットしなければなるまい。4,000万人の人口減少が起きるということは、絶対的なお金の量も今ほどは不要か、あるいは一人ひとりがお金持ちになっているかだが、恐らく前者だろう。 相対的価値観に沿って、お金と言うものを考え直し、輸出入においても縮小均衡を図らねばならない。生産性を限りなく向上させることは叶わない訳で、一定の賄いうる物に対しての輸出入の在り方が問われる。労働人口・海外拠点などの現在求められている企業の在り方も絶対的に縮小しなければ日本は成り立たなくなる。 国内サービス業の締める割合が飛躍的に増加し、介護サービスの充実・教育の付加価値付与に対する社会的ニーズの高まりも当然の帰結結果となろう。一方では文化的継承は現在と変わらず永続的に営まれ、心の充実感を味わう時代が到来するのではないか。 ひとくくりにすると、現在よりも生活の量的水準は下がるが、質の面で向上し、自給自足の機運が今までとは比較にならないほど進化する社会となっているのが50年後のように思われる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
東日本大震災のこれからを考える 平成23年4月17日 震災から1ヶ月余。激甚災害地の今後を考えている。人は危急の折にはアドレナリンが急放出される。このアドレナリンの放出は長くは続かない。興奮状態の次には、休息状態に入るのが生理的現象。即ち、被災者のアドレナリンはすでに枯渇しつつある。 私の経験では、当初の助け合いから、格差に気付き、やがて家族単位での行動となり、さらに格差は広がる。さらに、復旧から復興の時期にかかる頃には、震災の話題への忌避感が強くなる。格差は限りなく広がる。座標軸にプロットする点のように。底辺は浮かび上がることがない。被災者一人一人の点には、人数分の事なりがある。その事実に気付いた時、あろうことか、人々は黙り込んでしまう。そして人に助けられ、人を救う限界があり、自力で這い上がらねばならないことに気付く。災害弱者の虚しい現実がある。格差は時を経て広がる。被災していない地域とは、もっと格差が広がっているが、誰もそんなことは口にしない。仕方がない事と諦めるようになる。被災者全員共有していることは、被災体験を思い出し、「懐かしいな~!あの時、あの頃!」とは決して思わない事だ。 東日本大震災の今後を考える際に、極めて重要な事は、持続的にあるいは永続性を持たせた支援だと思われる。同時に、被災者自身が自立して行く時間経過の中では被災者を目に見えない自立を促す方法も活性化しなければならない。時間の経過とともに、そろりと密かに縁の下で様々な形の支援継続が必要だろう。物理的支援と精神的支援があるが、どちらも被災者の立場では不十分と感じるだろう。結局は自立再建という道しか無い訳で、やがて被災者自身震災には蓋をして封印しようとする行動と精神状態となる。こういう道筋を通ることは自明であり、支援の在り方も、そういう状況に添った形となる筈である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
東日本大震災と阪神淡路大震災 平成7年1月17日午前5時47分 激しい縦横揺れと大音響の中で私はベッド枠に腹ばいでしがみ付いていた。私が住む地は、震度7の大激震に見舞われていた。多くの家屋が倒壊し、神戸市内では最も多数の死傷者が出た所。阪神淡路大震災を経験し、人生観が大きく変わった。生きる者として、あれほどの厄災は再び見聞きすることは無いだろうと思っていた。 想像を絶する東日本大震災に接し、言葉が無い。私達が経験した阪神淡路大震災とは震災規模・範囲・状況が全く異なっている。阪神淡路では津波も原発事故もなかった。一面の荒野となった津波被害地の映像は、地震と言う概念を覆すものだ。尊い命を奪っただけではなく、地面ごと、あらいざらい根こそぎ海に流された街。虚無感という言葉では表すことのできない荒涼とした風景に絶句する。 被災者への持続的支援の輪を広げ、復興へまっしぐらに突き進むためにも、日本を襲った2度の厄災に対して、個人的ではあるが雑駁な記録をとどめておこう。
☆阪神は10㎞×2㎞・東日本は数百㎞×数十㎞ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
日本国を考えてみよう 平成23年4月21日 情報混乱を来している東日本大震災での救援の不手際には、日本国の弱点が信じられないほど露呈されている。 日本は技術大国として世界に冠たる立場を築き上げたかに見えていた。しかし、福島原発事故の惨憺たる状況に国民は唖然としている。何故なら、初動から現在まで後手後手にまわり、司令塔の存在が不明確、情報収集と集約がいまだに適格ではない。様々な産業分野、研究での先進的な内容を聞かされ続けてきた国民は、ロボットさえ米国に頼らざるを得ない現状に茫然自失。恐らく、先進的な技術開発は各地各部署で維持管理されているのだろうが、そういうものの一元管理なり、総合的視点での活用の能力が欠けているのだろう。現在もなお指示命令を待っている企業団体はあるのかもしれない。国家的指揮命令機能が機能していない上に、情報を一元管理する筈の内閣危機管理室の実態が明らかにされていない。総理が全てを掌握出来る訳もなく、指揮命令系統を多元化し、各大臣以下所轄に檄を飛ばし、責任をみずからに集中することぐらいはできるだろう。 無人ヘリの輸出禁止を決めた過去の報道も記憶に新しい。あのヘリはどこに行ったのだろう?今回の原発事故が想定されていなかったとしても、ロボット先進国日本で直ちに米国が提供した移動式カメラロボットぐらい作れるだろう。北朝鮮監視偵察衛星はどこへ行った?福島第一の映像提供されているのか?防衛秘密かもしれないが、それならそれで「きちんと宇宙から監視し続けています」などの政府広報があっても良いだろう。ありとあらゆる指示とお願いを産業界にしたのか!今からでも遅くない、やれる事は全て実行しなければならない。系統だった指示が出ているのだろうか?我々が日頃よく経験することは「誰かがするだろうと考え、我々にも能力はじめ技術もノウハウもあるが、求められてもいないことに勝手に動けない」という日本人気質がある。情報を一元化出来るシステムがなければすべて宝の持ち腐れになる。これほど苛立つ事態に国民は黙っていてはいけない。 震災から6週間を経て、次第に報道も静かになりつつある。このままで良いのか、良い訳がない。今は失敗を恐れず勇猛果敢に攻める日本国の在り方を問わねばならない。何が何でも原発は終息させるという気迫が伝わってこない。災害対策・原発対応・緊急経済問題対応の3つの部署を至急立ち上げ、権限を付与する特命チーム創出が喫緊課題だ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
聖徳太子十七条憲法第一条] 平成22年9月6日 以和爲貴 人間、恨みつらみは忘れず生涯続くものでしょう。虚しいことです。 聖徳太子の十七条憲法第一条に「和をもって貴しとし、逆らうることなきを旨とせよ 人皆党有り また達る者少なし 上和らぎ下睦みて、事をあげつらうにかなうときは、事理自らに通う。何事か成らざらん」と記されているようです。 党派根性に縛られることなく、上下の別なく互いに穏やかな心で議論をしなさい、そうすれば自ずと解決するものだと諭すものです。 太古の昔から、こういう争いが絶えなかったということなのでしょう。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
孔子像 平成22年8月30日
「西のバイブル ・ 東の論語」と称されている。 日本は中国の文化を上手に日本的に昇華してきた。現代日本は中国とは異質のように感じるが論語の世界は今でも色濃く継承している国柄。 孔子像を表しているものに、「子、四を断つ。意なく、必なく、固なく、我なし」というものがある。
・・・という四つのことを指すらしい。 また、温かさのなかに厳しさがあり、威厳がありながら威圧感がなく、謙虚でありながら堅苦しい感じを与えなかったと、弟子たちが評している。 いずれも、私に欠けることばかりだ。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
レンズを通さないで見る眼 平成22年8月23日 レンズを通すと必ず歪が生じる。レンズを通さないで直視することの重たさが求められる。右に左に大きくぶれる現実こそ生きている人間の悩みなのだろう。レンズを通した富士山の写真を見ても、綺麗だなと思うが、感動までは与えてくれない。実際に、この目で見た富士山は例え新幹線車内からガラス越しに見ても感動する。あぁそうなのか、これが霊峰富士か~、と思うのである。 人間、一つの事象に遭遇すると、とかくシャカリキになりがち。それが本来の闘争本能であり、生き抜く術、性とも言える。恐らく、それを忘れた自分は自分らしくない抜け殻でもあるだろう。生きている自分がそこにいるのなら、多少の犠牲心・義侠心が備わっていなければならないとも考える。どう思い、どう行動するかにかかっている。 戦争に負けても現代日本のように良い国もあるではないかと言ふ人もいる。ある意味間違いではないが、負けたという心は未だに日本人の心にネガティブに様々なことが働いている。勝って死んでも本望だと、何が何でも遣り通さなければとも思う。 仏教用語に「無相」という語がある。一方で人の路を諭されている自分がいる。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
終戦65年とお盆を思う 平成22年8月16日 中年を過ぎた頃から終戦記念日とお盆は重なる行事として深く考えるようになった。14日夜放映されたテレビドラマ「きこく歸國」を見た。重く受け止める内容だった。が、合間のコマーシャルの内容との余りにものギャップにさらに心は沈んだ。 親父が生きていた頃は、家庭の中で、親父だけの座があった。家族の誰もが座れない空間。親父は茶の間の最も良い場所に陣取り、自由気ままに家長としての威厳を放っていた。親父は座わったり横になったり、煙草を吸ったり、「お茶!酒!飯!」と、単語だけ発していた。かたや自分はどうだろう。定位置席はない。風来坊のようにあっちこっちへ…、冷蔵庫からビールを出し、コップを引っ張り出し冷酒を飲む。 時代は変わり、英霊への感謝の気持ち、祖先への畏敬の念は希薄になった。でも私は仏壇に手を合わせ親父に語りかける「引き上げて来て、俺を生んでくれて有難う!英霊の皆々様、日本の今を有難うございます!」と。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
楽に生きる 平成22年8月9日 今の日本は実に暗い。何だかドンドン日本は劣等国になり下がって行くような報道ばかり。個人所得も落ち込み、失われた20年・デフレスパイラルとか、ネガティブなフレーズが並ぶ。政治も混迷を極め、政府に地方行政に民は苦言を呈す。どうも自信のない国になってしまった。歯科医療の困窮をアピールするまでもなく、国民全体が困窮する事態を迎えている。さてどうするか!?個人の在り方を考えてみよう。 「明日は今日より必ず良い日が来る!」と言い聞かせ、朗らかな笑顔で毎日を過ごす。気力を充実させて、気持ちを変えることで、どうせお金がなくても、不幸に見舞われていると錯覚していても、笑えばきっと楽になる。落ち込んでいてはいけない。鏡の前で思いっきり笑ってみよう。きっと明日の勇気が湧いてくる。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
汽水漂う・漲る(ミナギる)島(邦 くに) 平成22年8月2日 汽水とは淡水と海水が交じり合う水のことをいう。すなわち、川が海に流れ込むその場所の水のことである。この汽水こそが、山の栄養を海にもたらす源であり、汽水により豊かな海が創られる。 山の栄養で大切なものは、樫・クヌギ・楓などの常緑広葉樹林のことであり、桧・杉などとは違う。広葉樹は冬には枯葉を落とし、その地面を腐葉土とする。そこでは動植物の連鎖、輪廻転生が繰り返され、それらを含んだ雨水が海に注ぎ込む。このようなつながりにより、日本の近海は豊かな海として醸成され続けている。汽水漂う国は自然がもたらした誠に有り難い環境である。 その環境が損なわれつつある現在、地球温暖化問題よりも重大な日本人の課題と見定めなければならない。 杉・桧の大規模植林が戦後行われた結果、花粉を撒き散らす大きさに育った杉・桧が、現在花粉症として国民を苦しめている。 (住宅街が山に迫っていることにも一因がある。神戸でも山沿いより海沿いの住民の花粉症は少ない。) ようやく、地域によって杉・桧を伐採し、広葉樹植林が行われつつある。 50年の計を見誤ると花粉症どころではない、日本という国の存亡に関わる事態がたくさん存在する。 予見出来ないこともある。青アスベストは肺胞に取り込まれてしまうサイズだから生体にダメージを加える結果となったと言われる。だからインクリボン粒子も肺胞に取り込まれないサイズまでが開発限界とされている。 差し迫った医療問題が山積している。未来につながる新しいシステム構築が私たち医療者の大きな責務だと思う。英知漂い・漲る那で在り続けたいものだ。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
「形あるものは壊れる」・・・!? 平成22年7月26日 表題は、誰しも理解しているつもりだ。 無機有機を問わず、いずれ無くなってしまう。 観念的ではなく、現実的理解が追い付いていない自分が居る。 パソコンの耐用年数は大凡5~6年であり、保守対応も次々と打ち切られて行く。 現在、ウインドウズMEのサポートは無い。XPもいずれはサポートが打ち切られるだろう。 一方、レセプトコンピューターはどうだろう? 漠然とベンダー主導で導入し、リース・アップになれば再びあれやこれやと悩み、挙句の果てに新規契約。 使い勝手が変わり、スタッフ共々あたふた。 今回のオンライン化に伴う措置についていけない、という声もいまだに多い。 今後、情報管理という意味において、作り上げることにも増して、潰れていく運命の情報を、どういう具合に保存するのか破棄するのか、皆で考えていかねばならないだろう。 壊れた陶器を捨てられずにいる、いっそ粉々になったら捨てられるのにな~・・・!?
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
江戸吉原 平成22年7月20日 たまに、日歯役員で私的交流の機会を持つことがある。 今回は、東京の常務が珍しいお店を吉原近くで設定してくれた。 一日に予約一組みのみ受け付けの、季節料理屋さんだ。 店内はこぢんまりして、囲炉裏を囲む風情あるたたずまい。 10数名で満席となるような規模だ。 我々7名は囲炉裏を囲みその日のお任せ料理に舌づつみ、会話も弾む。 特別珍しい料理という訳でもないが、美味しく頂戴した。 吉原は現在では寂れている。 当時の面影はないとのこと。 思い出したことがある。 半年ほど前に放映されていた連続ドラマ「仁」。 現代の医師が江戸時代にタイムスリップし、様々な活躍をする面白いものだった。 中でも吉原と花魁が大きくクローズアップされており、野風という花魁が登場する。 江戸の匂いは、まだ薫り続けている。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
遥か遠き思い出 平成22年7月12日 今年の梅雨は、雨が多い。 お陰で、おんぼろ我が家は雨漏りでとうとう大修理の憂き目。 当分、不自由な生活が待っている。 工事のために整理整頓をし、捨てるものの選別をと業者から指示あり。 昔のがらくたを整理していたら、小さいころからの様々なものが出てきた。 目を通していると、思わず目を覆いたくなるほど稚拙な私が居た。忘れていた頃を過去の資料が思い出させてくれた。懐かしい思い出というより、苦い思い出が多い。 今を美化しようとする者の特性から、ほとんど捨てることにしたが、残しておくものの一つとして写真を一枚見つけた。 恥ずかしくて、中身は言えない。 とにかく、お宝発見には至らなかった。 残念!
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
見張り 平成22年7月5日 航海での見張りは大切な役割。例えていうなら、今の歯科医療の見張り役は誰だろう!? 見張りは航海の進路を注視し、危険を未然に察知し、舵を切る操舵手に指示を出す。船の位置は?機関の不具合は?燃料は十分か?操舵だけではなく全乗組員が一丸となり航海の安全を遂行する。船という単体では見張りの役割や安全な航海というものがよく理解できる。 歯科医療という連続性があり蛇のようにうねりながら進む立体感覚の見張りは難しい。後ろを振り返り、長く横幅があり歪なものを全て見ることは不可能だし、前を向いてゆく手を阻むものは何処と見つめることも不可能。様々な要件を入力して分析を試みても中々困難な状況だ。日本の行く末と同じということぐらいしか分からない。 歯科医療は日本の歩む道とイコールなのだから、我々歯科医療人も日本の国をよりよく理解し、日本を考えることが歯科医療を考えることだと思考回路を変えなければいけない。 日本人として責任のある行動をすることが歯科医療の未来を明るくすると信ずる。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
アナログとデジタル化 平成22年6月28日 デジタル化全盛期の昨今、アナログとデジタルが全く別次元のものと混乱している向きもあります。 手で文字を書くこと、IT用機器を用いない状態をアナログ。電気信号変換で演算処理能力を飛躍的に向上させ、ある目的の事に対して迅速適格に処理することがデジタル化。 すなわち、世界中の事象はアナログですが、その一部のものを取り上げて高速処理して一元化すれば、より良い状況となるということでしょう。 膨大な文字情報・画像情報を一元化し瞬時に世界中から集めるためにはパソコンという端末が非常に便利となっています。 しかし、忘れてはいけないことがあります。自然界のほとんどの現象や人がそれをとらえる方法はアナログ的です。 つまり、絵画や音楽などは自然界の音や色を人がアナログ的に処理することから芸術として発展してきました。 大切なことはアナログ的大きな視野に立ち、今まで処理不能だったことに対して、目的を持ってデジタル化することと思います。 医療はアートとも言われ、極めてアナログ的なものです。「あらゆる芸術の士は人の世をのどかにし、人の心を豊かにするが故に尊い」と、かの夏目漱石は書いています。 歯科医療というものを考えるヒントがアナログとデジタルに潜んでいるのかもしれません。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
動物の本性 平成22年6月21日 政権与党内で党首が変わり総理大臣も8ヶ月で退任しました。 さすがに、8ヶ月は早すぎると思います。日本の立ち位置は混迷を極めているように映ります。さて、これからどうなるのでしょう!? 最近、テレビで動物の生態についての様々なドキュメンタリーが放映されています。概ね、食べること・生殖継体・子育て・安全性に焦点が合わされているようです。 しかし、根本は「生きること」すなわち「食べること」と見てとれます。我が家の犬達も同様で、24時間の内20時間ぐらいは寝ていますが、反面、食べる時間は短いにもかかわらず、その瞬間は全精力を注ぎ込みドッグフード茶碗に首を突っ込んでおります。 人間はどうでしょう。少々食べることを軽んじていないでしょうか。飽食の時代が続き、食べられることは当り前で、「食べること」について真剣に考えることが欠けている時代となったともいえます。 もっと、「食べること」と真剣に向きあいたいと思います。私たち歯科医師は人間の尊厳・原点である「食べること」をサポートする職種ですね。 そういう認識をもって、疾病に対する治療だけではないたとえば「食べること」についての社会的啓発活動をすることも歯科医師の務めだろうと思っています。
この中に、我が家のシェパードが・・・ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||